こんにちは!飲食業界で25年、お客様の「美味しい」とスタッフの「楽しい」を追求し続けてきた飲食店経営伴走型パートナー、岡本です。
飲食店の売上管理って、単に「今日いくら稼いだか」を記録するだけじゃないですよね。
僕は25年間、飲食業界の最前線で現場と経営の両方を見てきましたが、売上管理は飲食店経営の要。お店を長く続けていくための「健康診断」みたいなものなんです。数字をきちんと見ることで、お店の状態を定期的に確認して、問題があればすぐに対策を打てるようになります。
「なんとなく忙しいから大丈夫」なんて感覚だけで経営してると、気づいたときには手遅れ…なんてことも。

売上管理の本質は「利益」を管理すること。売上が好調でも経費が膨らんでいれば、実は赤字…なんてことも珍しくありません。だから単に数字を集めるだけじゃなく、その数字から問題点を見つけて改善していくプロセスが大切なんです。
この記事では、僕の経験をもとに、飲食店の売上管理の基本から効果的な分析手法まで、現場目線でわかりやすく解説していきます。
売上管理が飲食店経営に欠かせない3つの理由
「売上管理って面倒くさいな」って思う方も多いと思います。でも、これをしっかりやるかやらないかで、お店の未来が大きく変わってくるんですよ。
大型店舗をやっていた経験から言うと、売上管理がしっかりできている店舗とそうでない店舗では、危機対応力に雲泥の差がありました。
1. 経営状態を正確に把握できる
売上データをグラフ化すると、売上が下がるポイントが一目瞭然。「あれ?この時期いつも売上下がるな」とか「このイベントがあると売上上がるな」みたいな相関関係がすぐわかります。
経費データも細かく集計すれば、「この原材料、最近高くなってない?」とか「この時間帯、人件費に対して売上低すぎない?」みたいな無駄な支出も見えてきます。
僕が店長時代、手書きのノートで原価管理してた頃から大事にしてたのは、数字を「見える化」すること。見えないものは管理できないんですよね。
2. 問題点を早期発見・早期解決できる
売上管理をしっかりやってると、ちょっとした変化にもすぐ気づけます。
例えば、「先週から平日ランチの客単価が200円下がってる」ということに早く気づければ、「新メニューが受け入れられてないのかな?」とか「競合店ができたのかな?」って原因を探って、すぐに対策打てますよね。

逆に売上管理をおろそかにしていると、「なんか最近お客さん減った気がする…」って感覚的に気づいたときには、すでに大きな問題になってることも。
飲食店って、小さな問題の積み重ねで大きな危機になることが多いんです。だからこそ、数字で早期発見することが大事なんですよね。
飲食店の売上管理に必要なデータと記録方法
「売上管理って何から始めればいいの?」って思う方も多いと思います。
実は、最初から完璧を目指す必要はないんです。まずは基本的なデータをコツコツ記録することから始めましょう。僕も最初は手書きのノートから始めましたからね。
管理すべき基本データ
飲食店の売上管理で最低限押さえておきたいデータは以下の通りです。
- 日別・時間帯別の売上金額
- 来客数と客単価
- メニュー別の売上個数と金額
- 決済方法別の売上(現金・クレジットカード・QR決済など)
- 原材料費(仕入れ)
- 人件費
- 固定費(家賃・水道光熱費など)
特に大事なのは「売上=来客数×客単価」という基本の公式。売上が下がったとき、「来客数が減ったのか」「客単価が下がったのか」で対策が全然違ってきますからね。

記録方法の選択肢
売上データの記録方法は、大きく分けて以下の3つがあります。
1. エクセルなどの表計算ソフト
初期費用がかからず、自分好みにカスタマイズできるのが魅力。ただ、データ入力は手作業になるので、時間がかかります。
最近では、飲食店向けの無料テンプレートもネット上で公開されているので、それを活用するのもアリ。僕も昔はエクセルで原価計算してましたね。
例えば、このようなサイトから無料でダウンロードできますよ。⇒売上高・客単価一覧表(飲食業用)
2. 専用の売上管理アプリ
スマホやタブレットで簡単に記録できるアプリが増えています。月額制のものが多いですが、操作が簡単で、グラフ化やレポート作成も自動でやってくれるので便利です。
特に複数店舗を経営している場合は、リアルタイムで全店舗の状況を把握できるのが大きなメリット。
エクセルでデータ入力や煩雑な作業が億劫な人はこのようなアプリで管理することで余計な手間や時間を浪費せずに済むと思います。
3. POSレジシステム
レジと連動しているので、売上データが自動で記録されるのが最大の魅力。初期費用はかかりますが、長い目で見ると作業時間の削減になります。
最近のPOSレジは、売上管理だけでなく、在庫管理や顧客管理、スタッフのシフト管理までできるものも。うまく活用すれば、経営の効率化につながります。
飲食店の売上管理は売上分析がカギ!手法4選
データを集めただけじゃ意味がないんです。
そのデータをどう分析して、経営改善につなげるか。ここからが本当の売上管理の醍醐味だと思います。
25年間、現場でもまれてきた経験から言うと、難しい分析手法より、シンプルで実践的な方法のほうが効果的です。ここでは、飲食店でぜひ活用してほしい分析手法を4つ紹介します。
1. ABC分析(売れ筋商品の把握)
メニューを売上高や利益率で「A・B・C」の3つにランク分けする方法です。
例えば:
- Aランク:売上の70%を占める上位20%のメニュー
- Bランク:売上の20%を占める中間30%のメニュー
- Cランク:売上の10%を占める下位50%のメニュー
これをやると、「どのメニューに力を入れるべきか」「どのメニューを見直すべきか」が一目瞭然になります。
僕がコンサルティングしたある居酒屋では、ABC分析をしたら、実はあまり売れていないのに手間がかかるメニューがいくつもあることが判明。それらを整理して、Aランクのメニューに注力したら、売上は変わらないのに利益率が10%も上がりました。
2. RFM分析(顧客分析)
「Recency(最終来店日)」「Frequency(来店頻度)」「Monetary(購入金額)」の3つの指標で顧客を分析する方法です。
例えば、「最近来てないけど、以前は頻繁に来てくれていた常連さん」を見つけ出して、DM送ったりクーポン出したりして呼び戻す施策が打てます。
ポイントカードやオーダーアプリを導入していれば、この分析がやりやすくなりますね。
3. 時間帯・曜日別分析
いつ、どれくらいお客さんが来るのか。これを把握することで、効率的なシフト配置や、閑散時間帯の集客施策が打てます。
例えば、「月曜の夜は来客数が少ない」ということがわかれば、その時間帯限定のクーポンを出したり、SNSで告知したりして集客につなげられます。
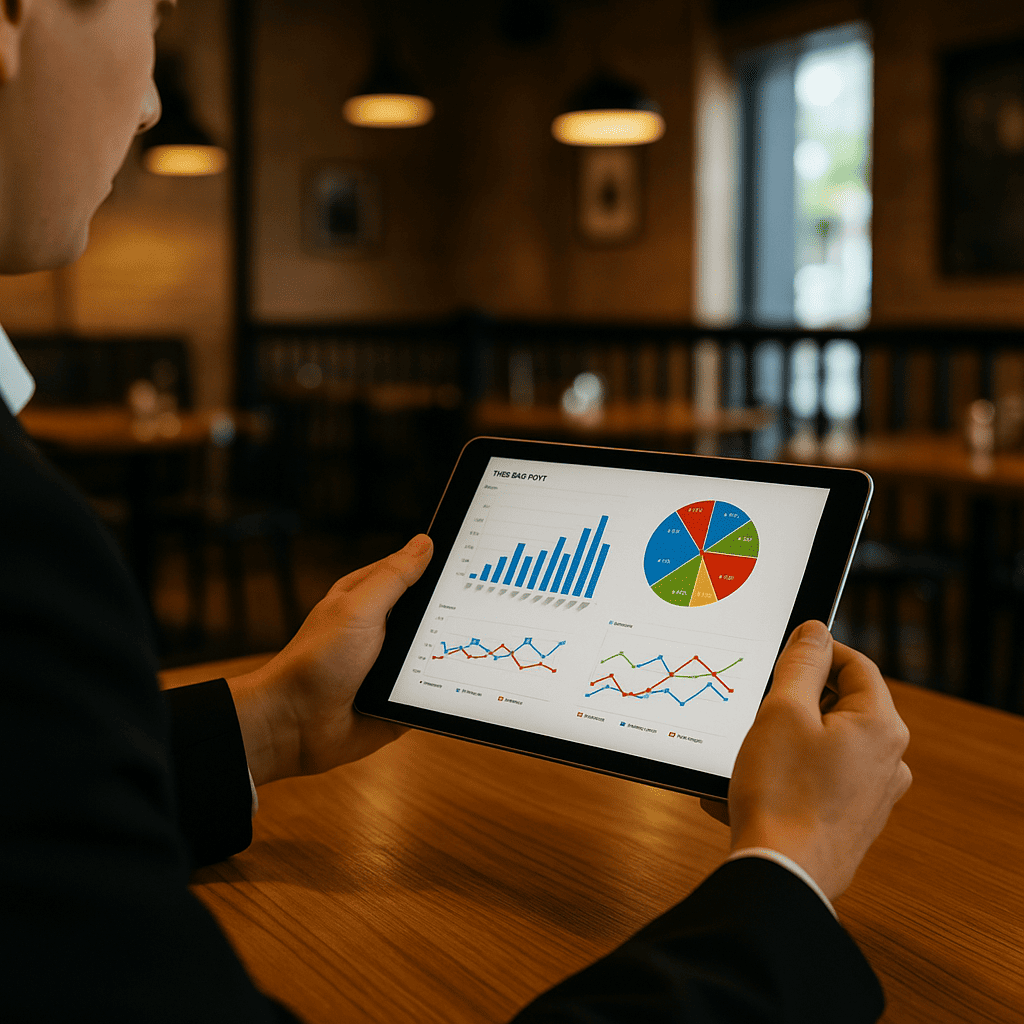
僕が現場にいた頃は、この分析をもとに「平日17時〜19時限定の生ビール半額」みたいな施策をやって、閑散時間帯の売上アップに成功しました。
4. バスケット分析(相性の良い商品の把握)
「この商品を注文したお客さんは、あの商品も一緒に注文することが多い」という相関関係を分析する方法です。
例えば、「生ビールを注文する人は枝豆も注文することが多い」ということがわかれば、メニュー表でその2つを近くに配置したり、セット販売したりすることで、客単価アップにつなげられます。
どうですか?
これらの分析方法、難しそうに聞こえるかもしれませんが、やってみると意外と簡単です。まずは自分のお店で試してみてください。きっと新しい発見があるはずですよ。
飲食店の売上管理データから見えてくる改善ポイント
売上データを分析すると、お店の改善ポイントが見えてきます。僕のこれまで経験から、よくある改善ポイントをいくつか紹介しますね。
データ分析って、単なる数字遊びじゃないんです。そこから具体的なアクションにつなげてこそ意味があります。
来客数が少ないときは?
売上データから「来客数が少ない」という課題が見えてきたら、以下のような改善策が考えられます。
- SNSでの情報発信強化(インスタ映えするメニューの開発など)
- 閑散時間帯限定のクーポンやサービスの提供
- 常連客向けの紹介キャンペーン
- Google マップやぐるなびなどの口コミ対策
僕が支援したあるラーメン店では、インスタ映えするトッピングを開発して、それをSNSで発信したところ、若い女性客が増えて客層が広がりました。
来客数は多いけど客単価が低いときは?
「来客数は多いけど客単価が低い」という課題が見えてきたら、以下のような改善策が考えられます。
- 高単価メニューの開発と推奨販売
- セット販売の強化
- ドリンクメニューの充実
- デザートなどの追加オーダー促進
居酒屋で働いていた頃、「生ビール頼んだお客さんには枝豆もおすすめする」というちょっとしたオペレーション変更だけで、客単価が平均で200円上がったことがあります。
売上がいいけど利益が出ない時は?
「売上はいいけど利益が出ない」という課題が見えてきたら、原価率を見直しましょう。
- 仕入れ先や仕入れ方法の見直し
- メニュー構成の見直し(高原価率メニューの価格改定など)
- 食材の無駄を減らす工夫(仕込み量の適正化など)
- 原価率の高いメニューと低いメニューのバランス調整
飲食店って、ちょっとした工夫で原価率を下げられることが多いんです。例えば、野菜の切り方を工夫するだけで歩留まりが上がったり、仕込みの量を適正化するだけで廃棄ロスが減ったり。
数字を見ながら、「どこを改善すれば効果的か」を考えることが大切です。すべてを一度に変えようとするのではなく、データに基づいて優先順位をつけて改善していきましょう。
売上管理を成功させるためのポイント
最後に、売上管理を継続的に成功させるためのポイントをいくつか紹介します。
僕も最初から完璧にできたわけじゃないんです。失敗しながら、少しずつ改善してきました。皆さんも無理せず、できることから始めてみてください。
1. シンプルに始める
最初から完璧な売上管理システムを目指さないこと。
まずは基本的なデータ(売上・来客数・客単価)だけでも毎日記録する習慣をつけましょう。慣れてきたら、徐々に記録する項目を増やしていけばOK。継続することが何より大切です。
2. 全スタッフで共有する
売上データやその分析結果は、店長だけでなく、全スタッフと共有しましょう。
「今月の目標」「先週の売上」「人気メニューランキング」などを朝礼で共有すると、スタッフのモチベーションアップにもつながります。
僕が店長をしていた頃は、毎日の売上目標と実績をスタッフルームに掲示していました。「自分たちの頑張りが数字になって見える」というのは、スタッフにとって大きなモチベーションになるんですよね。
3. 定期的に振り返る時間を作る
日々の忙しさに追われていると、データを記録するだけで終わってしまいがち。月に1回は必ず、データを振り返って分析する時間を作りましょう。
「先月と比べてどうか」「目標に対してどうか」「改善策は効果があったか」など、定期的に振り返ることで、PDCAサイクルを回せます。
4. 外部の視点も取り入れる
自分たちだけで分析していると、どうしても視野が狭くなりがち。時には税理士さんや中小企業診断士さん、同業の仲間など、外部の視点も取り入れると新しい気づきがあります。
僕も飲食業界の勉強会に参加して、他店の取り組みを聞くことで、「うちでもこれやってみよう」というアイデアをもらうことが多いです。
売上管理は、決して難しいものではありません。
| 大切なのは、継続することと、データから学び、行動に移すこと |
25年間飲食業界で働いてきた経験から言うと、「売上管理をしっかりやっているお店」と「そうでないお店」では、長期的に見ると大きな差が出てきます。特に不測の事態(外的要因、災害など)が起きたときに、その差は顕著になります。
まとめ|売上管理は“未来をつくる”ための習慣
飲食店の売上管理は、単なる数字の記録ではありません。それは、お店の“今”を正確に知り、“これから”をより良くするための習慣です。
忙しい日々の中で、つい感覚に頼ってしまいがちな経営。でも、その“なんとなく”を“確信”に変えるのが売上データの力です。
「いつ・何が・どうして」売上に影響しているのかを把握し、早めに手を打つ。小さな変化に気づき、少しずつ改善を重ねる。——それが、長く続くお店の共通点です。
大事なのは、完璧を目指すことより、まずは「続けること」。
紙のノートでも、エクセルでも、アプリでも。やりやすい方法で、小さく始めてみてください。きっと、数字が語りかけてくれるはずです。
「売上管理が経営のすべてを変える」
僕はそう信じていますし、現場で何度もその力を目の当たりにしてきました。
ひとりで悩まず、必要であれば僕のような伴走者も頼ってください。
“数字を味方にできる店”は、きっとどんな時代でも強くしなやかに生き残っていけます。
あなたのお店にも、そんな未来がきっと待っています。応援しています!
皆さんも、この記事を参考に、ぜひ自分のお店に合った売上管理を始めてみてください。わからないことがあれば、いつでも相談に乗りますのでぜひご相談ください!
飲食店の売上管理について、さらに詳しい情報や個別のコンサルティングをご希望の方は、飲食業界で25年、「美味しい」と「楽しい」を追求し続けてきた飲食店経営伴走型パートナー岡本にevisu公式LINEにてご相談ください。
岡本優
飲食店経営伴走型パートナー
もう、一人で悩まない。
あなたの店の「右腕」になります。
利益改善、集客強化、人材育成、オペレーション改善まで、
経営のあらゆる課題に、オーナー様と同じ目線で
共に答えを見つけ出します。
現場力とマーケティング力を掛け合わせた、
evisuだけが提供できる継続的なパートナーシップです。
飲食店の課題の答えは、すべて現場にあります。
私の仕事は、その答えをオーナー様と共に見つけ出すこと。
飲食業界で25年、お客様の「美味しい」とスタッフの「楽しい」を追求し続けてまいりました。株式会社サッポロライオン「銀座ライオン」にアルバイトにて入社後、ひたすら経営と現場に没頭する中で、新宿店、そして800席を超える銀座本店の総支配人を拝命。
赤字店舗の再建を託される機会も多く、お客様とスタッフ双方の満足度向上を軸としたアプローチで、全ての担当店舗を黒字化へ導いた経験は、私の大きな財産です。
しかし、多くの飲食店が未来に不安を抱えている現状を目の当たりにし、この経験を業界全体のために活かしたいという想いが日に日に強くなりました。そこで2025年、株式会社evisuを設立。25年間現場で培ったリアルなノウハウを、同じ志を持つ経営者の皆様と分かち合い、共に困難を乗り越えるパートナーでありたいと考えております。
「楽しくなければ飲食店ではない」を信念に、皆様のお店が笑顔で溢れる場所になるよう、全力でサポートいたします。



