こんにちは!飲食業界で25年、お客様の「美味しい」とスタッフの「楽しい」を追求し続けてきた飲食店経営伴走型パートナー、岡本です。
飲食業界で25年間、現場から経営まで幅広く経験してきた私が断言します。今、飲食店のオペレーションは大きな転換期を迎えています。
昔ながらの「マニュアル至上主義」から、柔軟で効率的な「新常識」へのシフトが急速に進んでいるんです。この変化に気づいていない店舗は、じわじわと競争力を失っていくでしょう。
私が飲食業界でアルバイトからキャリアをスタートした頃は、マニュアルを暗記し、先輩の動きを真似るのが「当たり前」でした。でも今は違います。テクノロジーの進化と人手不足という現実が、飲食店のオペレーションに新たな常識を生み出しているんです。

「でも、うちはマニュアルがしっかりしてるから…」
そう思っているオーナーさんこそ、この記事をぜひ読み進めてみてください。今日お伝えする「新常識」を知るだけで、あなたの店舗運営の視点が大きく変わるはずです。
なぜ今、従来の飲食店のマニュアル型オペレーションでは通用しないのか
私が25年間の飲食業界で目の当たりにしてきた最大の変化。それは「人」を取り巻く環境の激変です。
かつては「マニュアルを守れ」「先輩の動きを見て覚えろ」という指導が通用しました。800席の大型店舗でも、経験豊富なスタッフが多く、長時間労働もいとわない文化がありました。でも今はどうでしょうか?
人手不足は深刻化する一方で、短時間勤務のアルバイトが中心。教育に割ける時間は限られ、覚えることが多すぎるマニュアルはむしろ現場の負担になっています。
さらに、コロナ禍を経て「非接触」「省人化」のニーズが一気に高まりました。Web検索結果を見ても、多くの飲食店がDXやデジタル化に取り組んでいることがわかります。

「でも、うちはまだ紙のマニュアルとオーダー伝票で十分回ってるよ…」
本当にそうなのでしょうか? 実は気づかないうちに、スタッフの負担は増え、お客様の期待値とのギャップは広がっているかもしれません。
私が経験したことですが、マニュアルが多すぎると新人スタッフは読む前に挫折します。そして中途半端な理解のまま現場に立つことで、ミスやトラブルが発生するんです。
これからの時代、求められるのは「覚える」ことではなく「必要な時に必要な情報にアクセスできる」環境づくりなんです。
飲食店オペレーションの新常識①:標準化からパーソナライズへ
従来の飲食店オペレーションといえば、「標準化」が絶対でした。私も店長時代、スタッフ全員が同じ動きをできるよう、何度も何度も研修しました。
でも今、最先端の飲食店が取り入れているのは「パーソナライズされたオペレーション」です。
これはどういうことか?
スタッフの強みを活かす新発想
スタッフを「オールラウンダー」にするのではなく、得意分野に特化させる方法です。
例えば、人と話すのが好きなスタッフはホールに、細かい作業が得意な人は調理場に。さらに、ホールでも「案内係」「オーダー係」「会計係」と役割を明確にすることで、覚えることを減らし、早く一人前になれる環境を作るんです。
私は飲食店のキャリアはアルバイトからスタートしました。当時は「できるようになるまでこの仕事をさせるな」という考え方でした。でも今は違います。得意なことから始めて、少しずつ範囲を広げていく。これが新しいオペレーションの考え方です。

お客様視点のパーソナライズ
もう一つの新常識は、お客様一人ひとりに合わせたサービスです。
最新のDXツールを活用すれば、お客様の好みや来店履歴を簡単に管理できます。例えば、顧客情報を自動でタグ管理し、「初回来店者限定クーポン」や「レビュー投稿で10%オフ」などの特典を簡単に設定できるんです。
「常連さんには前回と同じドリンクをさりげなく提案する」
「アレルギー情報を記録して次回から自動的に注意喚起する」
といった、ちょっとした気配りが可能になっています。
これは、昔ながらの「名物店主」が持っていた記憶力と気配りを、テクノロジーで再現しているんですよね。 スタッフもお客様も、一人ひとりの個性を大切にする。これが新時代のオペレーションの第一歩なんです。
飲食店オペレーションの新常識②:自動化と人の強みの最適バランス
「全部機械に任せればいい」
これは大きな誤解です。私がコロナ禍で感じたのは、飲食店の価値は「人の温かみ」と「効率性」のバランスにあるということ。
新しいオペレーションの常識は、「機械にできることは機械に、人にしかできないことは人に」という明確な役割分担です。
機械化すべき3つの業務
多くの飲食店が自動化・機械化に取り組んでいます。特に効果が高いのは以下の3つです。
- 「注文・会計業務」
チェーン展開をしているある飲食企業では、セルフオーダーシステムの導入で待ち時間が50秒以内に短縮された例もあります。私の経験でも、注文受けと会計で店員の労力の40%近くが使われていたので、この部分の自動化は大きな効果があります。 - 「在庫・発注管理」
かつて、多くの飲食店ではノートで原価管理をしていました。今ではAIが需要を予測し、適切な発注量を提案してくれるシステムがあります。食品ロス削減にも大きく貢献します。 - 「調理の一部自動化」
配膳ロボットやオートフライヤー、オートコンベクションなど、品質を均一に保ちながら効率化できる設備が増えています。

人にしかできない3つの価値
一方で、機械には絶対に真似できない「人にしかできないこと」もあります。
- 「状況判断と臨機応変な対応」
お客様の表情から不満を察知したり、特別な要望に柔軟に応えたりするのは人間にしかできません。 - 「感情的なつながりの創出」
「いつもありがとうございます」という一言、名前を覚えてもらえる喜び、ちょっとした会話の温かみ。これらは機械では代替できない価値です。 - 「創造性と改善提案」
現場からの「こうしたらもっと良くなるかも」という提案は、店舗進化の原動力です。
私が現場で経験したのは、マニュアルを超えた「気づき」の大切さでした。例えば、常連のお客様の好みを覚えておいて、来店時に「いつものでよろしいですか?」と声をかける。こういった小さな気配りが、お客様の心をつかむんです。
結局のところ、新しいオペレーションの常識は「機械と人間の共存」。それぞれの強みを最大化することで、スタッフの負担は減り、お客様満足度は上がるんです。
飲食店オペレーションの新常識③:固定マニュアルからフレキシブルシステムへ
「マニュアルは本当に必要ないの?」
そう思った方もいらっしゃると思います。私が言いたいのは、「分厚い紙のマニュアル」ではなく、「状況に応じて最適な情報にアクセスできるシステム」が必要だということです。
マニュアルの問題点
従来型のマニュアルには、いくつかの致命的な問題があります。
まず「情報量が多すぎる」こと。
私が新人だった頃、100ページ以上あるマニュアルを渡されて「全部覚えろ」と言われました。でも実際に必要なのは、その時々の状況に応じた数ページ分の情報だけだったんです。
次に「更新が遅い」こと。
メニュー変更やキャンペーンのたびにマニュアル改訂が必要になり、最新版と旧版が混在する混乱も経験しました。
そして「個人差に対応できない」こと。
同じ説明でも、理解度や得意分野は人それぞれ。一律のマニュアルでは、誰かにとっては難しすぎ、誰かにとっては簡単すぎるということが起こります。
フレキシブルシステムの具体例
Web検索結果にもあるように、最新のオペレーション改善では「システム化・自動化」が重要なポイントになっています。
例えば、タブレットやスマホで必要な時に必要な情報だけを確認できるデジタルマニュアル。動画や画像を使った視覚的な説明で、言葉だけでは伝わりにくい「コツ」も共有できます。

また、AIを活用した意思決定支援システムも注目されています。例えば、天候や曜日、イベント情報から来客数を予測し、最適な人員配置や仕込み量を提案してくれるツール。私が店長時代に経験した「勘と経験」による判断を、データで補強してくれるんです。
さらに、クラウドカメラを活用した店舗管理も効果的です。Web検索結果にある「塚田農場」や「レッドロブスター」の事例のように、リアルタイムで店舗状況を確認し、適切な指示出しができるようになります。
「でも、そんなシステム導入するのにお金がかかるんじゃ…」
確かに初期投資は必要かもしれません。でしょう?でも、人手不足による機会損失や教育コスト、ミスによる損失を考えると、長期的には大きなリターンが期待できます。実際、私が関わった店舗では、オペレーション改善により売上が15%向上した例もあります。
明日から実践できる!新常識の飲食店オペレーションの始め方
「理想はわかったけど、具体的に何から始めればいいの?」
そう思った方のために、明日からすぐに実践できるステップをお伝えします。
ステップ1:現状分析と課題の可視化
まずは現場の声を集めることから始めましょう。
「今、最も時間がかかっている作業は何か」「よく起こるミスやトラブルは何か」を洗い出します。
私がよく使うのは「付箋紙ワークショップ」です。スタッフ全員に付箋を配り、思いつく課題を書いてもらう。そして似た内容をグループ化すると、自然と優先順位が見えてきます。
現場にいた時も、こうしたミーティングで「オーダーミスが多い」という課題が浮かび上がり、伝票の様式変更という小さな改善から始めたことがありました。
ステップ2:小さな改善から始める
全てを一度に変えようとするのではなく、最も効果が高そうな1つの改善から始めましょう。
例えば、Web検索結果にもある「ECRS」の考え方が役立ちます。
私の経験では、まず「S(簡素化)」から取り組むのが効果的です。例えば、複雑な手順を写真付きの簡易マニュアルにまとめるだけでも、新人の習熟度は大きく変わります。
ステップ3:テクノロジーの段階的導入
いきなり高額なシステムを導入するのではなく、無料や低コストのツールから試してみましょう。
例えば、LINEグループでのシフト管理やマニュアル共有、Googleフォームを使った在庫管理など、身近なツールでも十分効果があります。
私が以前関わった小規模飲食店では、iPadを1台導入し、写真付きの調理手順をいつでも確認できるようにしただけで、新人の習熟期間が半分になった例もあります。
ステップ4:継続的な改善サイクルの確立
最も重要なのは、一度改善したら終わりではなく、継続的に見直していく姿勢です。
「週1回の5分ミーティング」で改善点を話し合う習慣をつけるだけでも、オペレーションは少しずつ進化していきます。
私が大切にしているのは「現場の声を聞く」ことです。マネジメント側の理想論ではなく、実際に動いているスタッフの「こうしたら楽になる」という提案こそ、最も価値があります。
「楽しくなければ飲食店じゃない」というのが私の信条です。お客様にもスタッフにも、そして経営者自身にも楽しさを提供できるオペレーションこそ、これからの時代に求められる「新常識」なのではないでしょうか。

まとめ:マニュアルに頼らない、新時代の飲食店オペレーション
25年間の飲食業界経験から言えることは、「変化を恐れず、常に進化し続けること」の大切さです。
今回お伝えした飲食店オペレーションの新常識をおさらいしましょう。
①標準化からパーソナライズへ:スタッフの個性を活かし、お客様一人ひとりに合わせたサービスを提供する
②自動化と人の強みの最適バランス:機械にできることは機械に任せ、人にしかできない価値提供に集中する
③固定マニュアルからフレキシブルシステムへ:状況に応じて最適な情報にアクセスできる仕組みを作る
そして何より大切なのは、「小さな一歩から始める」という姿勢です。完璧を求めるのではなく、できることから少しずつ変えていく。その積み重ねが、結果として大きな変革につながります。
私自身、銀座でのオペレーション経験から、異業種のスタートアップを経て、今は個人飲食店オーナーの支援に取り組んでいます。その過程で痛感したのは、「現場を知り、数字も理解し、人の気持ちも大切にする」バランス感覚の重要性です。
飲食業界は今、大きな変革期を迎えています。でも、変化を恐れる必要はありません。むしろ、変化をチャンスと捉え、新しいオペレーションの形を模索していくことで、お店の可能性は大きく広がるはずです。
「楽しくなければ飲食店じゃない」
この言葉を胸に、これからも皆さんと一緒に、日本の飲食業界を盛り上げていきたいと思います。
飲食店経営に関するご相談や、オペレーション改善のサポートが必要な方は、飲食業界で25年、「美味しい」と「楽しい」を追求し続けてきた飲食店経営伴走型パートナー岡本にevisu公式LINEにてご相談ください。
岡本優
飲食店経営伴走型パートナー
もう、一人で悩まない。
あなたの店の「右腕」になります。
利益改善、集客強化、人材育成、オペレーション改善まで、
経営のあらゆる課題に、オーナー様と同じ目線で
共に答えを見つけ出します。
現場力とマーケティング力を掛け合わせた、
evisuだけが提供できる継続的なパートナーシップです。
飲食店の課題の答えは、すべて現場にあります。
私の仕事は、その答えをオーナー様と共に見つけ出すこと。
飲食業界で25年、お客様の「美味しい」とスタッフの「楽しい」を追求し続けてまいりました。株式会社サッポロライオン「銀座ライオン」にアルバイトにて入社後、ひたすら経営と現場に没頭する中で、新宿店、そして800席を超える銀座本店の総支配人を拝命。
赤字店舗の再建を託される機会も多く、お客様とスタッフ双方の満足度向上を軸としたアプローチで、全ての担当店舗を黒字化へ導いた経験は、私の大きな財産です。
しかし、多くの飲食店が未来に不安を抱えている現状を目の当たりにし、この経験を業界全体のために活かしたいという想いが日に日に強くなりました。そこで2025年、株式会社evisuを設立。25年間現場で培ったリアルなノウハウを、同じ志を持つ経営者の皆様と分かち合い、共に困難を乗り越えるパートナーでありたいと考えております。
「楽しくなければ飲食店ではない」を信念に、皆様のお店が笑顔で溢れる場所になるよう、全力でサポートいたします。

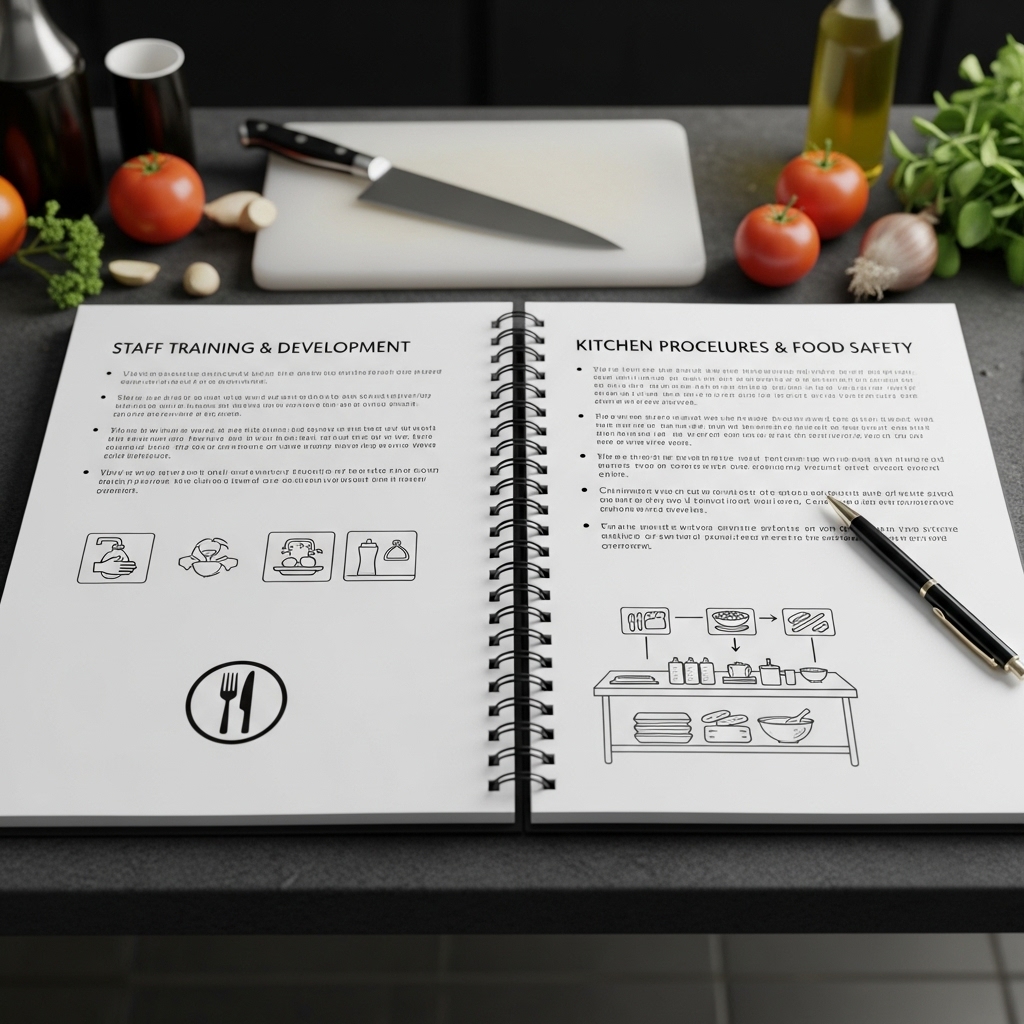
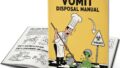

私が特に重視しているのは「現場からのフィードバックを即座に反映できる仕組み」です。マニュアルを一方的に押し付けるのではなく、現場の知恵を集めて常に進化させていく。これこそが、真のフレキシブルシステムだと思います。