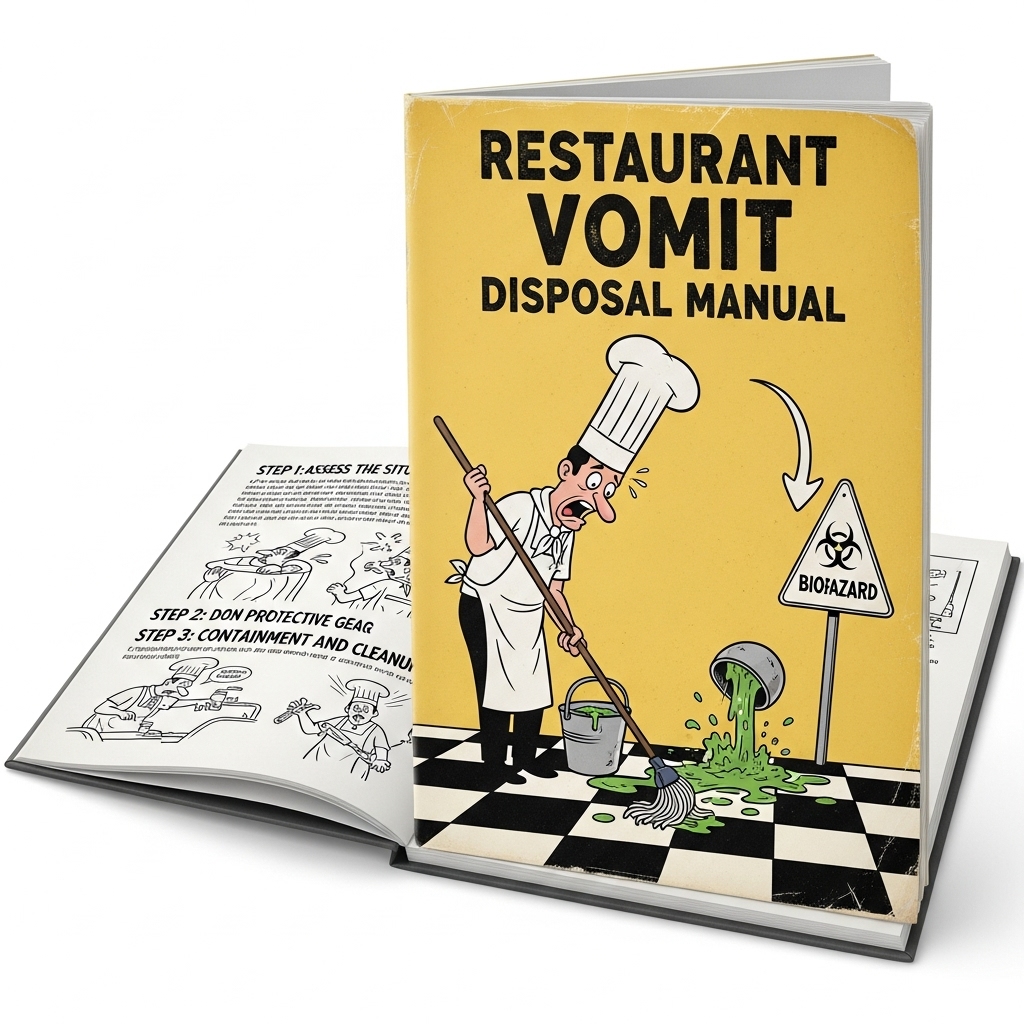こんにちは!飲食業界で25年、お客様の「美味しい」とスタッフの「楽しい」を追求し続けてきた飲食店経営伴走型パートナー、岡本です。
飲食店を経営していると、避けて通れないのが「お客様の嘔吐」です。特にお酒を提供するお店では、いつ起きてもおかしくない事態ですよね。
単にお酒の飲みすぎで気分が悪くなったケースでなく、もしそのお客様がノロウイルスなどの感染症にかかっていた場合、適切に処理しないと、あっという間に店内で感染が広がってしまうんですよ。
実は嘔吐物の処理って、多くの飲食店スタッフが「なんとなく」でやっていることが多いんです。でも、これは正しい知識と正しい手順に基づいて行わなければ、かえって感染を広げる原因になります。

飲食店で嘔吐事故が発生!その時あなたならどう対応する?
まず知っておいてほしいのは、嘔吐物の危険性です。特にノロウイルスなどの感染性胃腸炎の場合、嘔吐物には大量のウイルスが含まれています。
東京都健康安全研究センターの調査によると、1メートルの高さから嘔吐物が落ちると、なんと半径2メートルも飛び散ります。つまり、お客様が座った状態で嘔吐した場合でも、周囲のテーブルや壁、場合によっては天井にまで飛沫が到達する可能性があるのです。
参考元:東京都健康安全研究センター「ノロウイルス対策緊急タスクフォース」最終報告
あるお客様が突然嘔吐したことがありました。その時は見た目上、テーブルの上だけに収まったように見えたんです。でも念のため周囲も消毒したところ、なんと3メートル離れた別のテーブルにまで微細な飛沫が飛んでいたことが後からわかりました。
ノロウイルスの怖いところは、わずか10~100個のウイルスで感染が成立するほど感染力が強いこと。そして、アルコール消毒では効果が限定的なんです。
だからこそ、嘔吐物の処理は迅速かつ正確に行う必要があります。特に冬場はノロウイルスが流行するシーズン。お店の評判を守るためにも、お客様と従業員の健康を守るためにも、正しい知識を身につけておきましょう。
もし今、あなたのお店で嘔吐事故が起きたら、適切に対応できる自信はありますか?
嘔吐物処理に必要な準備を行う
嘔吐事故はいつ起こるかわかりません。だからこそ、事前に必要なものをセットにして準備しておくことが大切です。
僕が現場で培った経験から言うと、以下の11点を「嘔吐物処理キット」として常備しておくことをおすすめします。
- 使い捨て帽子 ×1
- 使い捨てマスク ×1
- 使い捨てエプロン ×1
- 使い捨て手袋 ×2セット(二重にするため)
- 使い捨て靴カバー ×1
- ポリ袋(大きめのもの) ×2
- 高吸収シートまたはペーパータオル(大量に)
- 紙製ヘラ(段ボールを切ったもので代用可)
- 次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)
- バケツ
- 注意喚起用の立て看板(「清掃中」など)
特に重要なのが「次亜塩素酸ナトリウム」です。家庭用の塩素系漂白剤(キッチンハイターなど)で代用できますが、濃度調整が必要です。ノロウイルスには1,000ppm以上の濃度が効果的とされています。
これらをすぐに持ち出せる場所に保管しておくことで、いざという時に慌てずに対応できます。
準備8割。これは現場で学んだ鉄則です。いざという時に「あれがない、これがない」となると、対応が遅れるだけでなく、パニックになりがちです。特に繁忙時間帯に嘔吐事故が起きた場合は、冷静さを保つためにも事前準備が命です。
嘔吐物処理の正しい手順
嘔吐物の処理は、単に拭き取ればいいというものではありません。感染拡大を防ぐためには、正確な手順で行うことが重要です。
まず、嘔吐があったら周囲のお客様を別の席に案内し、処理する区域を確保します。
次に、処理担当者を決めます。
担当者は以下の手順で処理を行います。
- 腕時計や指輪などのアクセサリーをすべて外す
- バケツにポリ袋を2枚重ねてセットする
- 帽子、マスク、エプロン、手袋(2枚重ね)、靴カバーを着用する
- 嘔吐物に高吸収シートをかぶせ、水分を吸収させる。
- 紙製ヘラで嘔吐物を集め、シートとヘラごとポリ袋へ回収する(飛沫が拡散しないよう注意)
- 1枚目の手袋を外して捨てる
- 次亜塩素酸ナトリウム希釈液をポリ袋の中身がまんべんなく濡れる程度に注ぐ
- ポリ袋(1枚目)の口を閉める
- 次亜塩素酸ナトリウム希釈液を床などの洗浄箇所にまんべんなくふりかける
- 外側から中央に向かって、新しい高吸収シートを使って拭き取る
- 使用したシートをポリ袋(2枚目)に捨てる
- 乾拭きや水拭きを行い、消毒剤を拭き取る
- 靴カバー、手袋、ガウン、帽子、マスクの順に外しポリ袋に捨てる
- 処理後は、しっかり手洗いを行う
これは厚生労働省のガイドラインに基づいた手順です。特に重要なのは、嘔吐物を拭き取る際に「外側から内側へ」向かって拭くこと。これにより、汚染範囲を広げずに処理できます。
また、消毒剤を10分間放置するのも重要なポイントです。次亜塩素酸ナトリウムがウイルスを不活化するには、一定の接触時間が必要なんです。
僕が現場で学んだコツとしては、処理中は周囲のお客様に不安を与えないよう、落ち着いた態度で対応することも大切です。パニックになると、かえって店内が混乱してしまいますからね。お客様の目の届く範囲(客席)での対応は少しアレンジも必要です。急にキャップ、エプロン姿の従業員が現れたら驚きますよね。気配りも重要です。
次亜塩素酸ナトリウム溶液の作り方
次亜塩素酸ナトリウム溶液は、市販の塩素系漂白剤(キッチンハイターなど)で代用できます。ただし、適切な濃度に薄める必要があります。
| 次亜塩素酸ナトリウム溶液とは、強力な殺菌・消毒作用を持つ液体で、主に漂白剤や消毒剤として使われます。家庭用では「ハイター」などが代表的です。 |
ノロウイルス対策には1,000ppm以上の濃度が必要です。
この溶液は時間が経つと効果が薄れるので、使用の都度作り直すことをおすすめします。また、作った溶液は必ず「次亜塩素酸ナトリウム溶液(漂白剤)」と明記し、誤飲防止のために安全な場所に保管してください。
次亜塩素酸ナトリウム溶液を使う際の注意点として、酸性の洗剤と混ぜると有毒ガスが発生するので絶対に避けてください。また、金属を腐食させる性質があるので、金属製の備品に使用する場合は、消毒後に水拭きをしっかり行いましょう。
嘔吐物処理後のフォローアップ
嘔吐物の処理が終わった後も、いくつかの重要なフォローアップがあります。
1.まず、嘔吐があった場所の周辺2メートル以内にあった食品や調味料、使い捨てでない食器などは、すべて廃棄または徹底的に消毒する必要があります。特に、嘔吐物が直接かかった可能性のある食品は、迷わず廃棄しましょう。
2.次に、処理に関わったスタッフの健康観察を行います。嘔吐物処理後24~48時間は、胃腸症状の有無を注意深く観察してください。もし症状が出た場合は、すぐに医療機関を受診し、飲食業務から外れることが重要です。
また、嘔吐事故があった場合は、その日のうちに全スタッフに情報共有を行い、手洗いの徹底など基本的な衛生管理を再確認することをおすすめします。

衛生管理は妥協できません。特に嘔吐物の処理は、お店の評判や営業継続に直結する重要な問題なんです。
感染症による嘔吐と飲みすぎによる嘔吐の見分け方
お客様が嘔吐した場合、それが単なる飲みすぎによるものなのか、感染症によるものなのかを完全に見分けることは難しいです。しかし、いくつかの目安はあります。
感染性胃腸炎(ノロウイルスなど)による嘔吐の場合、以下のような特徴があることが多いです。
- 突然の嘔吐(前兆があまりない)
- 下痢を伴うことが多い
- 発熱を伴うことがある
- 同行者にも同様の症状がある
- アルコール摂取量が少ないにも関わらず嘔吐している
一方、飲みすぎによる嘔吐の場合は、以下のような特徴があります。
- 大量のアルコール摂取後に起こる
- 嘔吐前に顔色の変化や冷や汗などの前兆がある
- 下痢や発熱を伴わないことが多い
- 嘔吐後に症状が改善することが多い
ただし、これらはあくまで目安であり、確実な判断は医療専門家にしかできません。そのため、安全を期して、すべての嘔吐物は感染性のものとして処理することをおすすめします。
以前ニュースで、とある飲食店でお客様が「ちょっと飲みすぎただけ」と言って嘔吐されたことがありました。その時は通常通り消毒処理をしたのですが、後日そのお客様から「実はノロウイルスだった」と連絡があったんです。このニュースから、原因に関わらず、すべての嘔吐物を感染リスクがあるものとして扱うことの重要性を学びました。
飲食店の嘔吐事故発生時にすべき他のお客様への対応
嘔吐事故が発生した場合、処理と同時に重要なのが、他のお客様への適切な対応です。
次に、処理中は該当エリアを立入禁止にします。可能であれば、パーテーションや衝立などで視界を遮ることも効果的です。これは、他のお客様の不快感を減らすだけでなく、飛沫の拡散防止にも役立ちます。
処理が完了した後は、移動していただいたお客様に丁寧にお詫びと説明をします。「ご不便をおかけして申し訳ございませんでした。安全のため、適切な消毒処理を完了しました」といった説明が適切です。
また、嘔吐物が飛散した可能性のあるエリアにいたお客様には、念のため手洗いをお勧めするとよいでしょう。
僕が経験した中で最も難しかったのは、満席時の嘔吐事故対応です。席の移動先がない場合は、一時的に立ち飲みスペースを設けたり、状況によっては割引券や次回使えるドリンクチケットなどでお詫びすることもありました。お客様の安全と満足度、両方を守るための臨機応変な対応が求められます。
衛生管理は手間がかかるからといって軽視できませんが、実は「正しく仕組み化する」ことで、感染リスクの低減だけでなく、スタッフの負担軽減や売上向上にもつながることをご存じですか?
衛生管理を簡略化すると売上が上がる?飲食店の新常識では、その仕組みづくりとメリットについて詳しく解説しています。現場の衛生対策を見直すヒントとして、ぜひ併せてご覧ください。
嘔吐事故を想定した訓練の重要性
嘔吐事故は、実際に起きてから対応を考えるのでは遅いです。事前に店舗スタッフ全員で対応手順を確認し、定期的に研修を行うことをおすすめします。
研修では、以下のポイントを押さえるとよいでしょう。
- 役割分担(誰が処理担当、誰が他のお客様対応など)
- 処理キットの保管場所と内容物の確認
- 次亜塩素酸ナトリウム溶液の作り方
- 処理手順の実践研修(水を使ったシミュレーション)
- 処理後の消毒範囲の確認
実際に水をこぼして、それを嘔吐物に見立てて実践研修すること。最初は「そこまでする必要ある?」という声もありましたが、実際に嘔吐事故が起きた時、研修していたスタッフは冷静に対応できます。
研修は面倒かもしれませんが、いざという時の「安心」を買う投資だと思ってください。お客様の健康と店舗の評判を守るための、最も費用対効果の高い取り組みの一つです。

まとめ:飲食店での嘔吐対応は準備と迅速な行動が鍵
飲食店での嘔吐対応は、お客様と従業員の健康を守り、店舗の評判を維持するために極めて重要です。
ポイントをまとめると
- 嘔吐物は半径2メートル以上に飛散する可能性があり、適切な処理が必須
- 処理キットを事前に準備し、いつでも使えるようにしておく
- 次亜塩素酸ナトリウム溶液での消毒が効果的
- 処理手順を守り、感染拡大を防止する
- 他のお客様への配慮と適切な説明も重要
- 定期的な実践研修で、いざという時の対応力を高める
25年間の飲食業界経験から言えることは、嘔吐事故は「起きるかもしれない」ではなく「必ず起きる」ものとして準備しておくべきだということ。特に冬場のノロウイルス流行期は警戒が必要です。
適切な準備と対応ができれば、嘔吐事故も怖くありません。むしろ、そんな時こそプロフェッショナルとしての対応力が試されるタイミングだと思っています。
楽しくなければ飲食店じゃない。その「楽しさ」を守るためにも、衛生管理の知識と技術を磨き続けましょう。
飲食店の衛生管理や運営についてさらに詳しく知りたい方は、飲食業界で25年、「美味しい」と「楽しい」を追求し続けてきた飲食店経営伴走型パートナー岡本にevisu公式LINEにてご相談ください。
岡本優
飲食店経営伴走型パートナー
もう、一人で悩まない。
あなたの店の「右腕」になります。
利益改善、集客強化、人材育成、オペレーション改善まで、
経営のあらゆる課題に、オーナー様と同じ目線で
共に答えを見つけ出します。
現場力とマーケティング力を掛け合わせた、
evisuだけが提供できる継続的なパートナーシップです。
飲食店の課題の答えは、すべて現場にあります。
私の仕事は、その答えをオーナー様と共に見つけ出すこと。
飲食業界で25年、お客様の「美味しい」とスタッフの「楽しい」を追求し続けてまいりました。株式会社サッポロライオン「銀座ライオン」にアルバイトにて入社後、ひたすら経営と現場に没頭する中で、新宿店、そして800席を超える銀座本店の総支配人を拝命。
赤字店舗の再建を託される機会も多く、お客様とスタッフ双方の満足度向上を軸としたアプローチで、全ての担当店舗を黒字化へ導いた経験は、私の大きな財産です。
しかし、多くの飲食店が未来に不安を抱えている現状を目の当たりにし、この経験を業界全体のために活かしたいという想いが日に日に強くなりました。そこで2025年、株式会社evisuを設立。25年間現場で培ったリアルなノウハウを、同じ志を持つ経営者の皆様と分かち合い、共に困難を乗り越えるパートナーでありたいと考えております。
「楽しくなければ飲食店ではない」を信念に、皆様のお店が笑顔で溢れる場所になるよう、全力でサポートいたします。