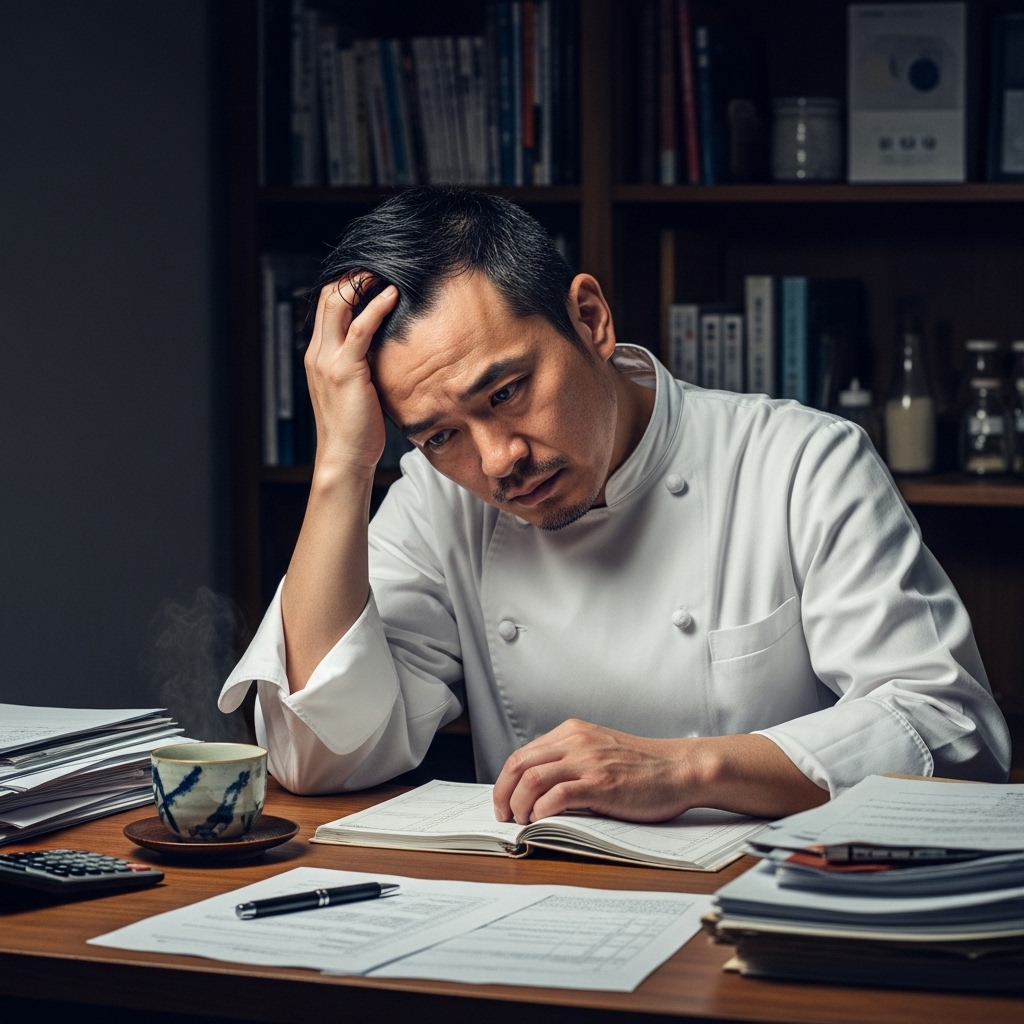こんにちは!飲食業界で25年、お客様の「美味しい」とスタッフの「楽しい」を追求し続けてきた飲食店経営伴走型パートナー、岡本です。
「飲食店を開業するなら、運転資金なんて必要ないよ」 こんな言葉を聞いたことはありませんか?
飲食店の開業では、初期投資だけでなく、しっかりとした運転資金の確保が成功への鍵になります。特に開業後3〜6ヶ月は売上が安定せず、予想外の出費も多いんです。

「でも、すぐに売上が立つから大丈夫」
この考え方が、多くの飲食店オーナーを苦しめる落とし穴になっています。
今回は、私の25年間の飲食業界経験から、運転資金の重要性と適切な資金計画について、実体験を交えてお伝えします。これから開業を考えている方も、すでにオープンして資金繰りに悩んでいる方も、ぜひ参考にしてみてください。
なぜ飲食店には運転資金が絶対に必要なのか?
まず最初に、運転資金とは何かを簡単に説明しておきます。
| 運転資金とは、店舗の日々の運営に必要なお金のことです。 |
具体的には、仕入れ、家賃、水道光熱費、人件費、広告宣伝費など、お店を回していくために必要な資金のことを指します。開業資金とは別に考える必要があります。

私が飲食業界で働いていた頃、新店舗のオープンに何度も関わりましたが、どんなに人気店でも、オープン直後から満席になることはほとんどありません。お客様に認知してもらい、リピーターを増やしていくには、最低でも3ヶ月、場合によっては半年以上かかるんです。
その間も家賃や人件費、仕入れ代金などの支払いは続きます。これらをカバーするのが運転資金なんです。
運転資金が不足すると起こる飲食店の悲劇
運転資金が不足すると、どんな問題が起きるのでしょうか?
私が以前サポートした新宿の居酒屋は、初期投資には1,500万円かけたものの、運転資金はわずか100万円しか用意していませんでした。オープン後、想定より集客に時間がかかり、2ヶ月目には仕入れの支払いができなくなってしまったんです。
結果、メニューを縮小せざるを得なくなり、それがさらにお客様離れを招く悪循環に。オープンからわずか4ヶ月で閉店することになりました。
これは決して珍しいケースではありません。
飲食店の開業において、運転資金の不足は「黒字倒産」という悲劇を招くことがあります。これは、売上は上がっているのに、資金繰りがうまくいかず、支払いができなくなる状態です。
飲食店を存続させるには実際に運転資金はどれくらい必要なのか?
-
では、具体的にどれくらいの運転資金が必要なの?
-
一般的には、最低でも月々の固定費(家賃、人件費、水道光熱費など)の3〜6ヶ月分は確保しておくべきです。例えば、月の固定費が100万円なら、300〜600万円の運転資金が必要になります。
ただし、これはあくまで最低ラインです。理想を言えば、6ヶ月〜1年分の運転資金を用意できると安心です。特に、季節変動の大きい業態や、商圏の形成に時間がかかるエリアでは、より多くの運転資金が必要になります。
成功する飲食店の運転資金~計画の立て方~
では、具体的にどのように資金計画を立てれば良いのでしょうか? 私の経験から、成功する飲食店の資金計画のポイントをお伝えします。
飲食店の開業において、しっかりとした事業計画書の作成は非常に重要です。特に資金計画は、事業の成功を左右する重要な要素となります。

私が140席のビアホールで店長をしていた頃、毎月の売上予測と実績を徹底的に分析していました。当時はノートに手書きで管理していましたが、この習慣が後々の経営に大いに役立ちました。
現実的な売上予測を立てる
資金計画の第一歩は、現実的な売上予測を立てることです。
多くの開業者が陥りがちなのが、売上を過大に見積もってしまうことです。「席数×回転率×客単価」で計算するのは基本ですが、開業直後から満席になることはほとんどありません。
私のアドバイスは、最初の3ヶ月は理想の売上の50%程度、次の3ヶ月で70%程度と、段階的に上げていく予測を立てることです。そして、その予測に基づいて必要な運転資金を計算していきます。
特に重要なのは、閑散期の売上予測です。例えば、8月や年末年始など、業態によって売上が落ち込む時期の資金繰りも考慮に入れておく必要があります。
売上予測を立てる際には、「どの時間帯・どの商品が売れているか」「原価や人件費と売上のバランスはどうか」といった売上管理の視点も欠かせません。売上データの見方や分析方法については、こちらの「【飲食店経営者向け】売上管理の基本と分析手法を徹底解説」も参考になると思います。
固定費と変動費を明確に分ける
次に、支出を「固定費」と「変動費」に分けて考えましょう。
- 固定費は、売上に関係なく毎月発生する費用です。家賃、人件費(最低限のスタッフ)、水道光熱費の基本料金、保険料、リース料などが含まれます。
- 変動費は、売上に応じて変動する費用です。食材や飲料の仕入れ、アルバイトの追加シフト、販促費などが該当します。
開業前に、これらの費用を詳細にリストアップし、月々どれくらいの支出が必要になるのかを把握しておくことが重要です。
どうでしょうか? 意外と細かい費用が多いですよね。
資金繰り表の作成と活用
資金計画の要となるのが「資金繰り表」です。これは、月ごとの収入と支出を予測し、手元資金の推移を管理するためのツールです。
資金繰り表を作成する際のポイントは、収入と支出のタイミングを正確に反映させることです。例えば、クレジットカード決済の場合、実際に入金されるのは1〜2ヶ月後になることもあります。また、仕入れ先への支払いサイトも考慮に入れる必要があります。
私が新宿の店舗を任されていた時、毎月の資金繰り表を作成し、3ヶ月先までの資金状況を常に把握していました。これにより、資金不足が予測される月には前もって対策を打つことができ、安定した経営につながりました。
こちらのマネーフォワードさんの記事が作成時に参考になると思います⇒資金繰り表とは?エクセルでの作り方・無料テンプレートも
運転資金の調達方法と活用のコツ
運転資金の重要性と必要額が分かったところで、次は具体的な調達方法について見ていきましょう。
飲食店の開業資金を調達する方法はいくつかありますが、それぞれにメリット・デメリットがあります。自分の状況に合った最適な方法を選ぶことが大切です。
自己資金と借入のバランス
理想的なのは、できるだけ自己資金で賄うことです。自己資金であれば、返済の必要がなく、金利負担もありません。
しかし、全額を自己資金で用意するのは難しいことも多いでしょう。その場合は、借入を検討することになりますが、自己資金と借入のバランスが重要です。
一般的には、総資金の30%以上は自己資金であることが望ましいとされています。例えば、開業資金と運転資金を合わせて1,500万円必要な場合、最低でも450万円は自己資金で用意できると、金融機関からの信頼も得やすくなります。
日本政策金融公庫の活用
日本政策金融公庫では、以前「新創業融資制度」という創業者向け融資制度がありましたが、令和6年3月31日をもって取り扱いを終了しています。そして現在はその代替として、「新規開業・スタートアップ支援資金」という制度が拡充されました。
この「新規開業・スタートアップ支援資金」は、最大7,200万円(うち運転資金4,800万円)まで借りられ、無担保・無保証人でも申し込めるケースが増えています。
返済期間も、設備資金は最高20年以内、運転資金は10年以内(据置期間最大5年)と長期返済が可能で、利率も最大で0.65%引き下げされる優遇があります。
審査では事業計画書や資金計画の具体性が重要で、運転資金の必要性や使途を明確にすることが求められます。
自治体の制度融資も検討する
各自治体でも、創業者向けの融資制度を設けていることが多いです。例えば、大田区では「開業資金」という融資あっせん制度があり、最大2,000万円まで融資を受けることができます。
自治体の制度融資は、地域によって条件が異なりますので、開業予定地の自治体のホームページなどで確認してみてください。中には、利子補給制度があるなど、有利な条件を提供している自治体もあります。
私がサポートした飲食店オーナーの中には、日本政策金融公庫と自治体の制度融資を組み合わせて資金調達をした方もいます。複数の融資を上手く組み合わせることで、資金調達の幅が広がります。
クラウドファンディングという選択肢
最近では、クラウドファンディングを活用して開業資金を調達するケースも増えています。特に、地域に根ざしたコンセプトの飲食店や、特徴的なメニューを提供する店舗などは、支援を集めやすい傾向にあります。
クラウドファンディングのメリットは、資金調達と同時に宣伝効果も得られることです。支援者は潜在的なお客様になる可能性が高く、オープン前から固定客を獲得できるチャンスでもあります。
ただし、目標金額を達成できなければ資金を受け取れない「All or Nothing」方式のプラットフォームもありますので、計画的に進める必要があります。
代表的なプラットフォームはこのとおり。

成功事例と失敗事例から学ぶ飲食店の運転資金の重要性
ここからは、私が実際に見てきた成功事例と失敗事例をご紹介します。他の方の経験から学ぶことで、自分の開業計画に活かしていただければと思います。
飲食業界で25年間働いてきて、様々なオーナーの成功と失敗を目の当たりにしてきました。その経験から、資金計画が店舗の命運を分けることを痛感しています。
成功事例:慎重な資金計画で安定成長を実現したラーメン店
私がサポートした東京郊外のラーメン店は、開業資金800万円に加えて、運転資金として600万円(月の固定費の6ヶ月分)を用意していました。
オープン当初は想定通り客足が伸び悩みましたが、十分な運転資金があったため、落ち着いて店舗運営に集中することができました。広告宣伝にも適切な投資を続け、口コミでの評判も徐々に広がっていきました。
結果的に、4ヶ月目から黒字化を達成し、1年後には当初の売上目標を上回るまでに成長しました。現在では2号店の出店も果たし、安定した経営を続けています。
このオーナーが成功した最大の要因は、十分な運転資金を確保していたことで、焦らず理想の店づくりに集中できたことだと思います。

失敗事例:運転資金不足で閉店に追い込まれたカフェ
一方で、都内のあるカフェは、内装や設備に1,200万円をかけたものの、運転資金はわずか100万円しか用意していませんでした。「オープンしたらすぐに売上が立つはず」という楽観的な見通しを立てていたのです。
しかし、実際にはオープン後の集客に苦戦。SNSでの宣伝も効果が出るまでに時間がかかり、2ヶ月目には家賃の支払いにも困る状況に陥りました。
急遽、追加融資を検討しましたが、開業間もないこともあり審査が通らず、結果的にオープンからわずか3ヶ月で閉店することになりました。
この失敗の最大の原因は、運転資金の重要性を軽視し、初期投資に資金を集中させてしまったことにあります。どんなに素晴らしい内装や設備でも、運転資金が不足していれば、ビジネスとして成立させることはできないのです。
資金計画の成功ポイント
これらの事例から学べる成功のポイントをまとめると、このようになります。
- 開業資金と運転資金を明確に区別し、両方に十分な予算を確保する
- 最低でも固定費の3〜6ヶ月分の運転資金を用意する
- 売上予測は保守的に立て、最悪のシナリオも想定しておく
- 資金繰り表を作成し、定期的に見直す習慣をつける
- 追加の資金調達手段も事前に検討しておく
飲食店経営において、お金の管理は料理の腕と同じくらい重要なスキルです。特に開業初期は、資金繰りに細心の注意を払うことが、生き残りの鍵となります。
まとめ:運転資金は飲食店成功の生命線
飲食店の開業において、「運転資金不要説」は危険な落とし穴です。25年間の飲食業界経験から断言できますが、十分な運転資金の確保は、成功への必須条件の一つです。
飲食店経営は、料理の美味しさだけでなく、堅実な資金計画があってこそ成り立つビジネスです。
これから開業を考えている方は、ぜひ運転資金の重要性を理解し、余裕を持った資金計画を立ててください。すでに開業している方も、今一度資金繰りを見直してみることをおすすめします。
飲食業界は厳しい世界ですが、それだけにやりがいもあります。適切な資金計画と情熱を持って取り組めば、必ず成功への道は開けるはずです。
飲食店の開業や経営でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。25年間の現場経験を活かして、あなたのお店の成功をサポートします。
飲食業界で25年、「美味しい」と「楽しい」を追求し続けてきた飲食店経営伴走型パートナー岡本にevisu公式LINEにてご相談ください。
岡本優
飲食店経営伴走型パートナー
もう、一人で悩まない。
あなたの店の「右腕」になります。
利益改善、集客強化、人材育成、オペレーション改善まで、
経営のあらゆる課題に、オーナー様と同じ目線で
共に答えを見つけ出します。
現場力とマーケティング力を掛け合わせた、
evisuだけが提供できる継続的なパートナーシップです。
飲食店の課題の答えは、すべて現場にあります。
私の仕事は、その答えをオーナー様と共に見つけ出すこと。
飲食業界で25年、お客様の「美味しい」とスタッフの「楽しい」を追求し続けてまいりました。株式会社サッポロライオン「銀座ライオン」にアルバイトにて入社後、ひたすら経営と現場に没頭する中で、新宿店、そして800席を超える銀座本店の総支配人を拝命。
赤字店舗の再建を託される機会も多く、お客様とスタッフ双方の満足度向上を軸としたアプローチで、全ての担当店舗を黒字化へ導いた経験は、私の大きな財産です。
しかし、多くの飲食店が未来に不安を抱えている現状を目の当たりにし、この経験を業界全体のために活かしたいという想いが日に日に強くなりました。そこで2025年、株式会社evisuを設立。25年間現場で培ったリアルなノウハウを、同じ志を持つ経営者の皆様と分かち合い、共に困難を乗り越えるパートナーでありたいと考えております。
「楽しくなければ飲食店ではない」を信念に、皆様のお店が笑顔で溢れる場所になるよう、全力でサポートいたします。