こんにちは!飲食業界で25年、お客様の「美味しい」とスタッフの「楽しい」を追求し続けてきた飲食店経営伴走型パートナー、岡本です。
飲食店経営者の皆さん、「売上は悪くないのに利益が出ない…」と悩んでいませんか?その気持ち、痛いほど分かります。
私も経験がありますが、飲食店経営で最も重要なのは「損益分岐点」を理解し、それを下げる戦略を持つことです。
損益分岐点とは、簡単に言えば「赤字と黒字の分かれ目となる売上高」のこと。これを下げることができれば、少ない売上でも利益を出せる強い店舗体質が作れるんです。
今回は、私が現場で培った経験から「損益分岐点を下げる7つの戦略」をお伝えします。どんぶり勘定から脱却して、しっかりと利益を生み出す店舗づくりを一緒に考えていきましょう!
損益分岐点とは?飲食店経営の要となる数字
損益分岐点って聞くと難しく感じるかもしれませんが、要は「お店が赤字にも黒字にもならない、ちょうどプラスマイナスゼロになる売上高」のことです。

飲食店経営において、この数字を知ることは非常に重要です。なぜなら、この数字を超えれば利益が出始め、下回れば赤字になるという、まさに経営の生死を分ける分岐点だからです。
例えば、月の固定費が100万円、変動費率が60%の店舗があるとします。この場合の損益分岐点は250万円。つまり、月商250万円を超えないと利益が出ないということになります。
損益分岐点の計算方法
損益分岐点の計算式はシンプルです。
| 損益分岐点 = 固定費 ÷ (1 – 変動費率) |
ここで重要なのは、固定費と変動費をしっかり理解することです。
固定費:売上に関係なく発生する費用
家賃、固定資産税、正社員の人件費、リース料、減価償却費、支払利息など、売上の増減に関わらず毎月一定額かかる費用です。私が店長だった頃、この固定費の大きさに頭を悩ませたものです。
変動費:売上に比例して変動する費用
原材料費、アルバイトの人件費、水道光熱費、消耗品費などが該当します。お客様が増えれば増えるほど、これらの費用も比例して増加します。
戦略1:メニュー構成変更で食材原価を最適化する
まず取り組むべきなのは、変動費の大部分を占める食材原価の最適化です。
単に原価率を下げるだけでなく、メニュー全体の構成を見直すことで、お客様満足度を維持しながら利益率を高めることができるんです。
ABC分析でメニューを見直す
メニューを「利益貢献度」と「人気度」で分類するABC分析は、非常に効果的です。
多くの店舗では、このD(ドッグ)に該当するメニューが意外と多いものです。ある居酒屋では、全メニューの約20%がこのカテゴリーに入っていました。これらを思い切って削減し、その分の労力をA(スター)メニューの品質向上に回したところ、原価率が5%も下がったんです。
食材の無駄を徹底的に減らす
食材ロスの削減も重要です。
具体的には、以下の取り組みが効果的です。
- 食材の発注量と在庫管理の徹底
- 仕込み量の適正化(売上予測に基づく調整)
- 食材の相互利用(あるメニューの副産物を別メニューに活用)
- 季節メニューの導入による旬の食材の活用
要は、一言でいうと「見える化」なんです。何がどれだけ使われて、どれだけ廃棄されているのか。この数字を把握することから始めましょう。

戦略2:人件費の最適化で固定費を変動費化する
飲食店経営において、人件費は通常、売上の30%前後が適正とされています。しかし、多くの店舗では35%を超えているのが現状です。
ある店舗は人件費率が40%もありました。これでは利益を出すのは難しい。そこで取り組んだのが「固定費の変動費化」です。
どういうことでしょうか?
正社員(固定費)とアルバイト・パート(変動費)のバランスを見直すことで、繁閑に合わせた柔軟な人員配置が可能になります。もちろん、単純に正社員を減らせばいいというものではありません。
人時生産性を高める工夫
重要なのは「人時生産性」という考え方です。これは、スタッフ1人が1時間あたりにどれだけの売上を生み出せるかという指標です。
例えば、以下のような取り組みが効果的です。
- オペレーションの標準化(マニュアル整備)
- 動線の最適化(無駄な移動を減らす)
- マルチタスク化(一人で複数の作業をこなせるようにする)
- 繁閑予測に基づくシフト管理
ある店舗では、徹底的に動線分析を行い、スタッフの移動距離を30%削減することに成功しました。これにより、同じ人数でより多くのお客様に対応できるようになったんです。
あなたの店舗では、スタッフの動きを観察したことがありますか?
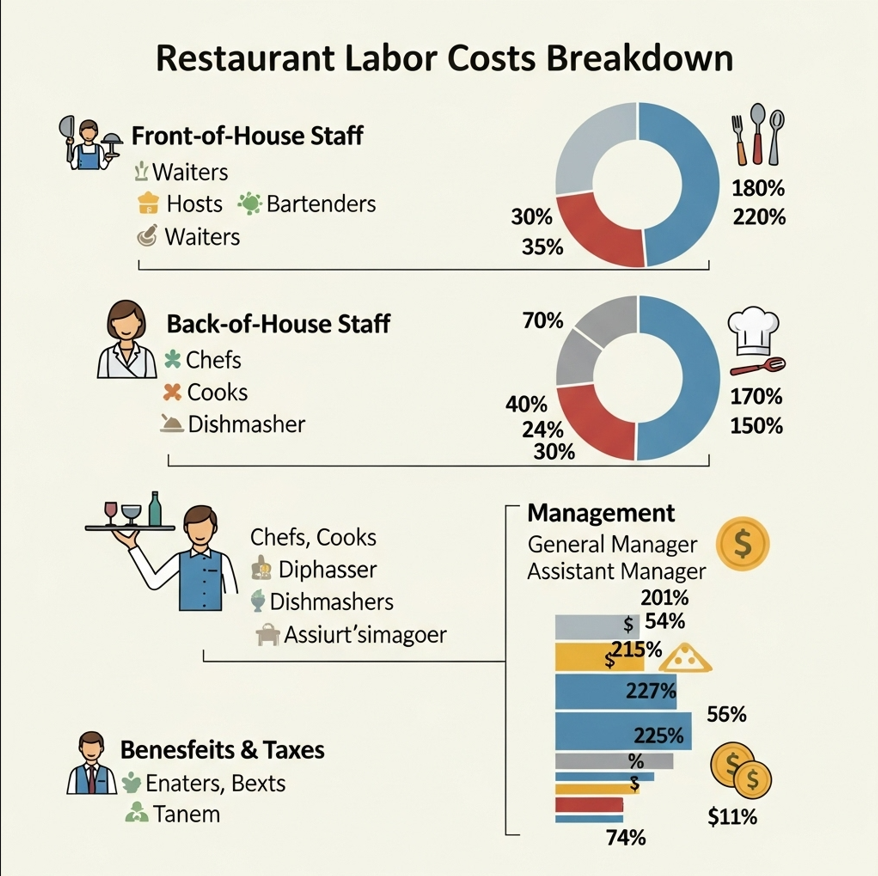
戦略3:固定費の見直しで損益分岐点を一気に下げる
固定費は、売上に関わらず発生する費用なので、これを削減できれば損益分岐点を大きく下げることができます。
家賃交渉と設備投資の見直し
飲食店の固定費で最も大きな割合を占めるのが家賃です。
コロナ禍以降、多くの不動産オーナーは柔軟な対応を示すようになっています。オーナーへの直談判で家賃の10%減額に成功したお店も。交渉のポイントは、長期的な関係性を強調することです。
また、設備投資やリース契約の見直しも効果的です。本当に必要な設備かどうか、リース期間や金利は適正かを再検討してみましょう。
水道光熱費の削減策
水道光熱費も見逃せない固定費の一つです。
- LED照明への切り替え
- 省エネ型厨房機器の導入
- ピーク電力の管理(一度に使用する電力量の調整)
- 水の再利用システムの検討
これらの取り組みは、初期投資が必要な場合もありますが、長期的に見れば大きなコスト削減につながります。
小さな削減の積み重ねが、大きな利益を生み出すんです。
戦略4:客単価アップで効率的に売上を増やす
損益分岐点を下げるためには、コスト削減だけでなく、効率的な売上アップも重要です。特に客単価アップは、来客数を増やすよりも効率的に売上を伸ばせる方法です。
追加おすすめの徹底で、客単価がアップし、利益率も大幅に改善したんです。
追加おすすめの実践
例えば:
ポイントは、お客様のニーズに合わせた自然な提案をすることです。押し売りではなく、「このワインは今日の料理と相性が良いんですよ」といった形で価値を伝えることが大切です。
高利益率メニューの開発と配置
メニュー構成も客単価アップの重要な要素です。
利益率の高いメニューを目立つ位置に配置したり、「シェフのおすすめ」として特別感を演出したりすることで、注文率を高めることができます。
また、季節限定メニューや「本日のスペシャル」といった希少性を感じさせるメニューも効果的です。京都の店舗では、毎週金曜日限定の「シェフの気まぐれ一品」を導入したところ、金曜日の客単価が約10%アップしました。
お客様は「特別なもの」に価値を感じるものです。あなたの店舗でも、そんな特別感を演出できる要素はありませんか?
戦略5:回転率の向上で固定費効率を高める
飲食店経営において、回転率の向上は利益率を大きく左右します。特に固定費の大きい店舗では、回転率を上げることで固定費効率を高めることができるんです。
オペレーション効率化のポイント
回転率を上げるためには、オペレーションの効率化が欠かせません。
- 注文から提供までの時間短縮
- 会計処理の迅速化(モバイルオーダー・決済の導入など)
- テーブルセッティングの効率化
- 厨房と客席の連携強化
ただし、回転率を上げることだけに注力すると、お客様満足度が下がる可能性があります。「急かされている」と感じさせないよう、自然な流れを作ることが重要です。
時間帯別の戦略設計
時間帯によって客層や滞在時間は大きく異なります。
例えば、ランチタイムは回転率重視、ディナータイムは客単価重視といった形で、時間帯別に戦略を変えることが効果的です。
ある居酒屋では、平日17:00〜19:00の時間帯に「90分飲み放題付き早割コース」を導入。これにより、従来は客足が少なかった時間帯の集客が増え、ピーク時間帯の混雑緩和にもつながりました。
あなたの店舗でも、時間帯別の戦略を見直してみませんか?
戦略6:テクノロジー活用で業務効率化と人件費削減を実現
飲食業界でも、テクノロジーの活用が当たり前になってきています。適切なテクノロジー導入は、業務効率化と人件費削減の両方を実現できる強力な武器になります。
私が働き始めた頃と比べると、今は本当に便利なシステムが増えました。ある飲食店では、セルフオーダーシステムの導入により、ホールスタッフを2名削減することに成功。その結果、損益分岐点が大幅に下がり、赤字を回避できたんです。
コスト削減につながるテクノロジー
特に効果的なのは以下のようなシステムです。
- セルフオーダー・セルフレジシステム
- 在庫管理システム(発注の自動化・食材ロス削減)
- シフト管理システム(人員の最適配置)
- 顧客管理システム(リピーター育成)
初期投資は必要ですが、長期的に見れば大きなコスト削減につながります。特に人件費の高騰が続く今、テクノロジー活用は避けて通れない課題です。
導入時の注意点
ただし、闇雲にテクノロジーを導入すれば良いというものではありません。
まずは自店舗の課題を明確にし、それを解決できるシステムを選ぶことが重要です。また、スタッフへの教育やお客様への説明も丁寧に行いましょう。
私が見てきた失敗例の多くは、「導入したはいいが使いこなせていない」というケースです。テクノロジーはあくまでツール。それを使いこなすのは人間です。
あなたの店舗では、どんなテクノロジーが課題解決に役立ちそうですか?

戦略7:リピーター育成で集客コストを削減する
新規客の獲得コストは、既存客の維持コストの5倍以上かかるといわれています。損益分岐点を下げるためには、リピーター育成による集客コスト削減が非常に効果的です。
顧客データの活用方法
効果的なリピーター育成には、顧客データの活用が欠かせません。
- 来店履歴・注文履歴の記録
- 誕生日や記念日の管理
- 好みのメニューや座席の記録
- アレルギーや食の制限の把握
これらの情報を基に、お客様一人ひとりに合わせたサービスを提供することで、「また来たい」と思ってもらえる店づくりができます。
効果的なリピーター施策
具体的なリピーター施策としては、以下のようなものが効果的です。
- ポイントカードやスタンプカード
- 会員限定メニューや特典
- 誕生日・記念日特典
- LINE公式アカウントを活用した情報発信
特にLINE公式アカウントは、低コストで効果的なコミュニケーションツールです。あるお店は、LINE会員向けの「本日の空席情報」配信により、平日の稼働率が向上しました。
お客様との関係づくりは、一朝一夕にはできません。地道な積み重ねが、やがて大きな成果につながるんです。
一緒に、強くて愛されるお店を作っていきましょう!
損益分岐点を下げる取り組みに興味がある方は、ぜひ個別相談にお越しください。あなたの店舗に合わせた具体的な戦略をご提案します。
飲食業界で25年、「美味しい」と「楽しい」を追求し続けてきた飲食店経営伴走型パートナー岡本にevisu公式LINEにてご相談ください。
岡本優
飲食店経営伴走型パートナー
もう、一人で悩まない。
あなたの店の「右腕」になります。
利益改善、集客強化、人材育成、オペレーション改善まで、
経営のあらゆる課題に、オーナー様と同じ目線で
共に答えを見つけ出します。
現場力とマーケティング力を掛け合わせた、
evisuだけが提供できる継続的なパートナーシップです。
飲食店の課題の答えは、すべて現場にあります。
私の仕事は、その答えをオーナー様と共に見つけ出すこと。
飲食業界で25年、お客様の「美味しい」とスタッフの「楽しい」を追求し続けてまいりました。株式会社サッポロライオン「銀座ライオン」にアルバイトにて入社後、ひたすら経営と現場に没頭する中で、新宿店、そして800席を超える銀座本店の総支配人を拝命。
赤字店舗の再建を託される機会も多く、お客様とスタッフ双方の満足度向上を軸としたアプローチで、全ての担当店舗を黒字化へ導いた経験は、私の大きな財産です。
しかし、多くの飲食店が未来に不安を抱えている現状を目の当たりにし、この経験を業界全体のために活かしたいという想いが日に日に強くなりました。そこで2025年、株式会社evisuを設立。25年間現場で培ったリアルなノウハウを、同じ志を持つ経営者の皆様と分かち合い、共に困難を乗り越えるパートナーでありたいと考えております。
「楽しくなければ飲食店ではない」を信念に、皆様のお店が笑顔で溢れる場所になるよう、全力でサポートいたします。



