こんにちは!飲食業界で25年、お客様の「美味しい」とスタッフの「楽しい」を追求し続けてきた飲食店経営伴走型パートナー、岡本です。
25年間、現場の最前線での経験から、今日は飲食店経営の厳しい現実についてお話しします。
飲食店は開業しやすい業種である反面、廃業率が最も高い業種でもあります。開業から3年以内の廃業率は70%、5年で80%、10年では90%以上と言われているほど、生き残るのが難しい世界なんです。
あなたも「美味しい料理を提供しているのに、なぜお客様が増えないんだろう」「毎月の経費に頭を悩ませている」といった悩みを抱えていませんか?
今回は、飲食店経営が難しい10の理由と、それを乗り越えるための具体的な戦略をご紹介します。私自身が経験した失敗や成功体験も交えながら、あなたの店舗運営に役立つ情報をお伝えしていきます。
飲食店経営の現実:なぜ多くの店が生き残れないのか
理由1:初期投資の負担が大きい
飲食店を開業する際、思った以上に多額の資金が必要になります。これが第一の難関です。
個人で飲食店を開業する場合、10坪〜15坪の店舗で1,000万円ほどかかってきます。居抜き物件やDIYで開業資金を抑えるやり方もありますが、それでも500万円ほどはかかるでしょう。

ある店舗では、厨房設備の老朽化が激しかったため、設備投資が必要でした。しかし、投資額が大きすぎて回収に時間がかかり、結果的に利益を圧迫することになったんです。初期投資は慎重に計画する必要があります。
初期投資の回収には通常2〜3年かかるため、その間の運転資金も含めた資金計画が必要です。理想のお店を作りたいという想いから、内装や家具、厨房機器などに費用をかけすぎるケースが多いのですが、投資額が大きくなるほど、回収にかかる時間も長くなります。
開業後すぐに黒字化できるケースはまれで、運転資金の不足は廃業リスクを高めます。必要額の目安や確保方法はこちらで詳しく解説しています。
▶ 飲食店は「運転資金不要説」の落とし穴と成功する資金計画とは?
成功への戦略としては、まず徹底した事業計画書の作成が不可欠です。開業資金や運転資金の内訳、売上予測、損益分岐点、資金調達計画などを具体的に盛り込みましょう。また、日本政策金融公庫などの公的融資や、補助金・助成金の活用も検討する価値があります。
理由2:運転資金の不足
開業できたとしても、軌道に乗るまでの運転資金が足りなくなるケースが非常に多いです。
飲食店は開業直後から黒字になることはほとんどありません。お店の認知度を上げ、常連客を獲得するまでには時間がかかります。その間の家賃、人件費、食材費などの固定費は毎月発生し続けます。

ある店舗では、店舗自体の魅力はあったのですが、開業時の資金計画が甘く、広告宣伝費が不足していました。結果として認知度が上がらず、当初の売上予測を大きく下回ることに。急遽、運転資金の追加調達が必要になりました。
成功への戦略としては、最低でも6ヶ月分の運転資金を確保しておくことが重要です。また、売上が安定するまでの間は、固定費を可能な限り抑える工夫も必要です。例えば、スタッフは必要最小限からスタートし、徐々に増やしていく方法や、食材のロスを減らすための仕入れ計画の最適化などが有効です。
あなたのお店では、運転資金の計画は十分にできていますか?
理由3:FLコストの管理が難しい
飲食店経営において、食材費(Food Cost)と人件費(Labor Cost)を合わせたFLコストの管理は非常に重要です。しかし、これが適切にコントロールできないことが多くの飲食店の経営を圧迫しています。
FLコストは経費の大部分を占めるため、このバランスが崩れると利益率が大きく低下します。一般的に、飲食店のFL比率は60〜65%が適正と言われていますが、これを維持するのは容易ではありません。
FLコストを適正化するためには、まず原価率や粗利率、利益率を正しく理解し、数値で管理することが重要です。
食材費は市場価格の変動に左右されますし、人件費は最低賃金の上昇や人手不足による採用コストの増加など、外部要因の影響を受けやすいのです。
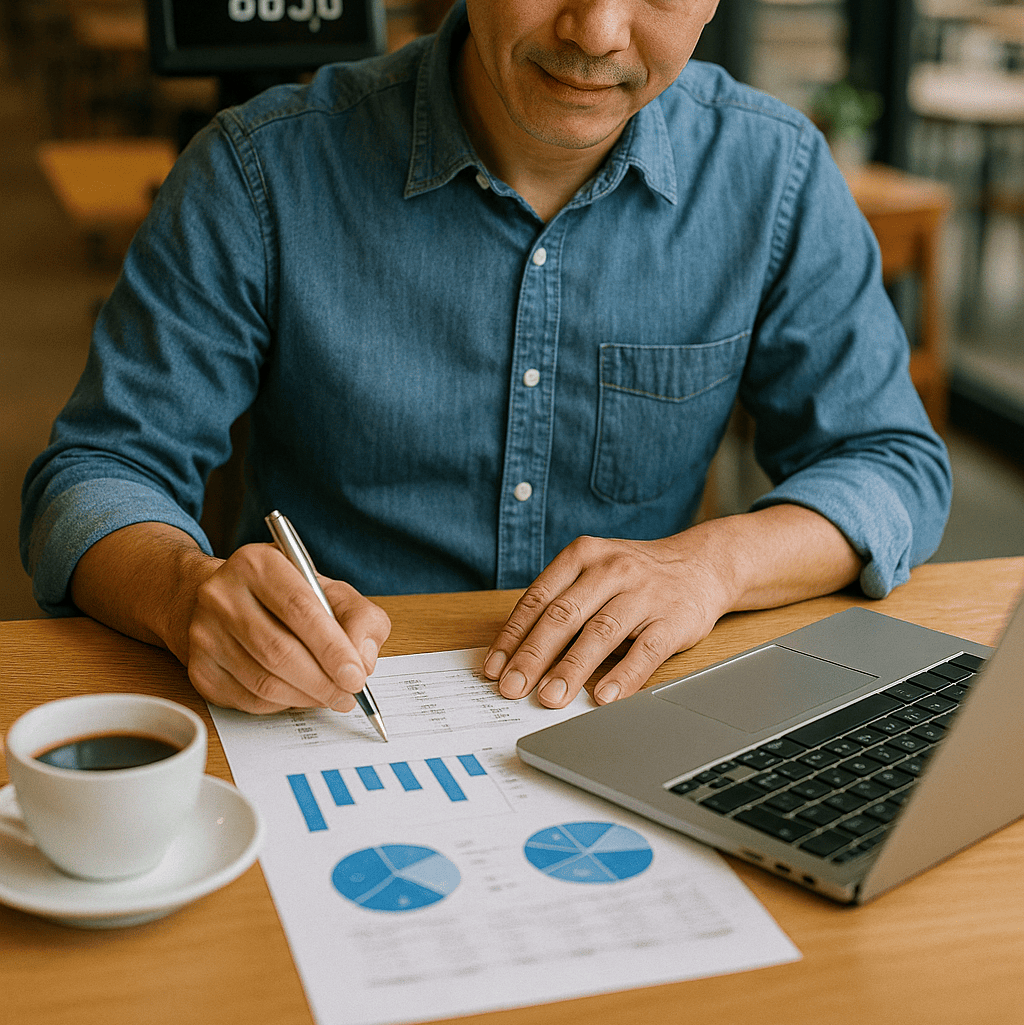
ある店舗では、季節ごとの食材価格の変動に対応できず、メニュー価格の見直しが遅れたことで、一時的に食材原価率が40%を超える事態になりました。これは飲食店経営では危険水域です。すぐにメニューの見直しと原価計算の徹底を行い、何とか立て直しましたが、日々の細かな管理がいかに重要かを痛感しました。
成功への戦略としては、まずABC分析による食材の分類と原価管理の徹底が挙げられます。また、人時生産性(1時間あたりの売上)を指標として、シフト管理を最適化することも効果的です。さらに、定期的なメニュー分析を行い、利益率の高いメニューを中心に構成を見直すことも重要です。
理由4:売上の外的要因による変動
飲食店の売上は、天候や季節、イベントなど、様々な外的要因によって大きく変動します。これらの要因をコントロールすることはできません。
雨が降ったり急激に寒くなったりすると客足が激減する店舗もあります。また、流行によって客足が一気に増減することもあるのです。
テレビや雑誌、SNSなどで店舗が話題になり、連日行列ができるほどの人気店になったものの、しばらくすると客足が減り、空席が目立つようになるというケースも珍しくありません。
ある日、テレビ番組で当店のメニューが紹介されました。翌日から2週間ほど、お客様が殺到し対応に追われましたが、その後は徐々に落ち着き、結局一時的なブームで終わってしまいました。メディア露出による売上増加は一時的なものであることが多く、持続的な集客戦略が必要です。

成功への戦略としては、まず売上の変動要因を分析し、パターンを把握することが重要です。天候や季節による変動に対しては、テイクアウトやデリバリーなど、来店に依存しない売上チャネルを確保することが有効です。また、季節ごとのイベントや限定メニューを計画的に導入し、閑散期の集客を強化する取り組みも効果的です。
売上の基準値や季節変動の影響度を数値化すると、改善策が見えやすくなります。
あなたのお店では、外的要因による売上変動にどのように対応していますか?
理由5:競合の多さと差別化の難しさ
飲食業界は参入障壁が低いため、競合が非常に多い業界です。食品衛生責任者が1店舗に1名いれば開業できますし、その資格は1日の講習で取得可能です。
また、ライバルは同じ飲食店だけではありません。中食の一般化やイートインスペースの設置の増加などから、コンビニエンスストアやスーパーマーケットなども競合となり得ます。
このような環境の中で、自店の独自性を打ち出し、差別化を図ることは非常に難しいのです。
ある店舗は、周辺に似たようなコンセプトの店が多く、集客に苦戦していました。そこで、地方での経験を活かし、各地の珍しい食材を使った「ご当地メニュー」を開発。これが好評を博し、差別化に成功しました。お客様は「ここでしか食べられない」体験を求めているのだと実感しました。

成功への戦略としては、まず徹底的な市場調査と競合分析を行い、ターゲット顧客を明確に定義することが重要です。その上で、そのターゲットに特化したメニュー開発やサービス提供を行い、独自のポジショニングを確立します。また、地域コミュニティとの関係構築や、特定の食材や調理法へのこだわりなど、自店ならではの「ストーリー」を持つことも効果的な差別化戦略となります。
理由6:人材確保と育成の難しさ
飲食業界は慢性的な人手不足に悩まされています。特に、シフト制の勤務体系や夜間・休日の労働が必要なことから、安定した人材確保が難しい業界です。
さらに、採用できたとしても、接客や調理のスキルを身につけるには時間がかかります。人材の定着率が低いことも、飲食店経営における大きな課題となっています。
あるスキー場のレストランでは季節限定の店舗だったため、短期間で新人スタッフを戦力化する必要がありました。そこで、作業を細分化し、写真付きの詳細なマニュアルを作成。さらに、先輩スタッフによるマンツーマン指導の時間を確保しました。この取り組みにより、新人スタッフの習熟度が大幅に向上し、早期戦力化に成功しました。

成功への戦略としては、まず魅力的な職場環境の整備が重要です。適正な賃金設定はもちろん、シフトの柔軟性や研修制度の充実など、働きやすさを追求することが人材確保の鍵となります。また、業務の標準化とマニュアル整備により、新人スタッフの早期戦力化を図ることも効果的です。さらに、スタッフのモチベーション維持のための評価制度や、キャリアパスの明確化も重要な要素となります。
あなたの店舗では、スタッフの採用や育成にどのような工夫をしていますか?
理由7:顧客ニーズの変化への対応
現代の消費者は情報感度が高く、多様な価値観を持っています。健康志向の高まりや、食の安全に対する意識の向上、SNS映えを重視する傾向など、顧客のニーズは常に変化しています。
これらの変化に対応し続けることは、飲食店経営者にとって大きな課題です。時代に合わせたメニュー開発や、サービス提供の方法を常に見直す必要があります。
健康志向の高まりに対応するため、カロリー控えめメニューの開発に取り組みました。しかし、当初は「味が物足りない」という声も多く、試行錯誤の連続でした。お客様の声を丁寧に聞き取り、何度もレシピを調整した結果、「美味しくてヘルシー」と評価されるメニューが完成。このプロセスを通じて、顧客ニーズの変化に対応するには、継続的な対話と改善が不可欠でした。

成功への戦略としては、まず定期的な顧客調査やフィードバック収集の仕組みを構築することが重要です。SNSの活用や、来店客へのアンケート、POS分析などを通じて、顧客の声や行動を継続的に把握します。また、トレンド情報にアンテナを張り、業界の動向を常に観察することも必要です。そして、収集した情報をもとに、迅速かつ柔軟にメニューやサービスを改善していく体制を整えることが成功への鍵となります。
理由8:デジタル化への対応
近年、飲食業界でもデジタル化が急速に進んでいます。オンライン予約システムやキャッシュレス決済、SNSを活用した集客など、テクノロジーを活用した経営が求められるようになっています。
しかし、多くの飲食店経営者にとって、これらのデジタルツールの導入や活用は容易ではありません。特に、長年アナログな方法で経営してきた店舗にとっては、大きな変革を求められることになります。
予約管理をアナログからデジタルシステムに移行する取り組みを行いました。当初はスタッフの抵抗も大きく、二重管理の状態が続いていましたが、成功事例を共有することで徐々に浸透。結果として予約ミスが激減し、顧客満足度の向上につながりました。デジタル化は一朝一夕には進みませんが、根気強く取り組む価値があります。
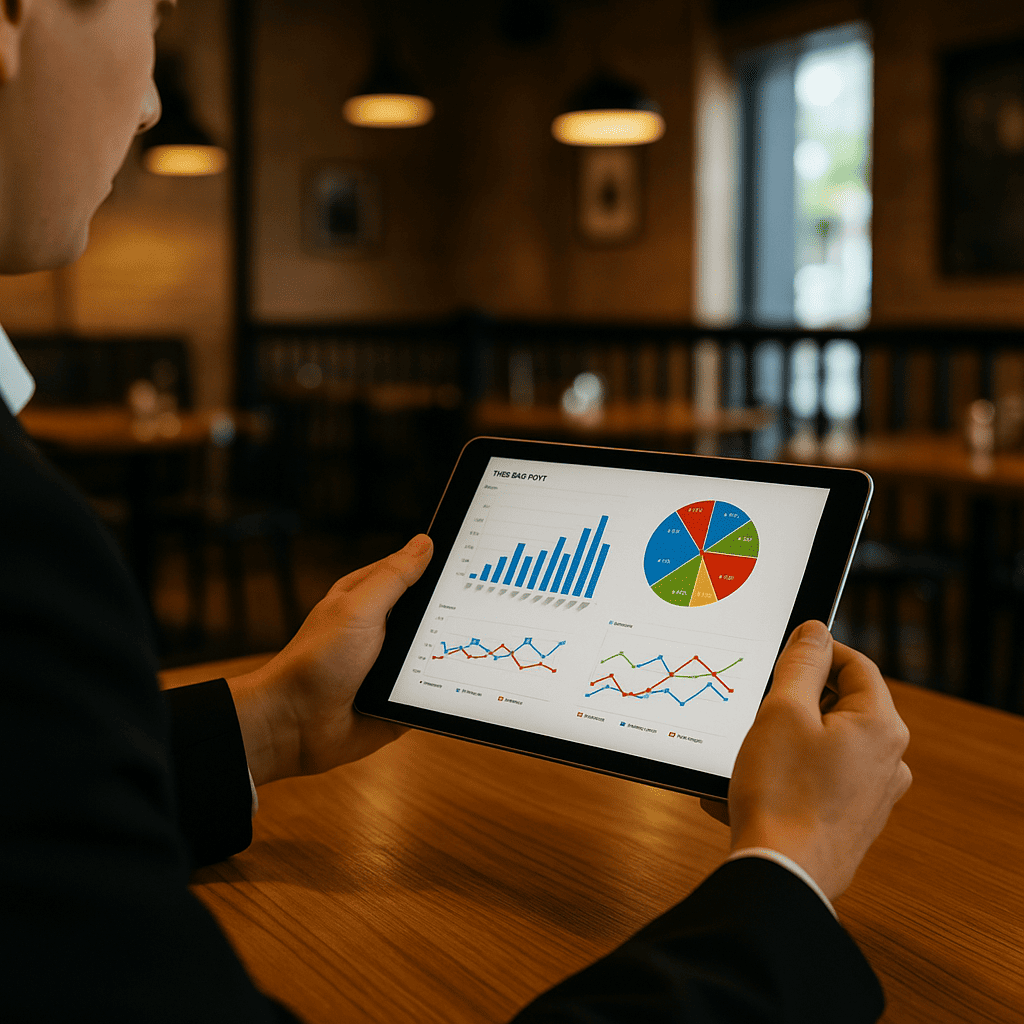
成功への戦略としては、まず自店の課題を明確にし、それを解決するためのデジタルツールを選定することが重要です。すべてを一度に導入するのではなく、優先順位をつけて段階的に進めることがポイントです。また、スタッフへの丁寧な説明と研修を行い、変化への抵抗を減らす工夫も必要です。さらに、デジタル化による効果を定量的に測定し、成功体験を積み重ねることで、組織全体のデジタルリテラシー向上を図ることが効果的です。
あなたのお店では、どのようなデジタルツールを活用していますか?
理由9:衛生管理と法令遵守の負担
飲食店は食品を扱う業種であるため、厳格な衛生管理が求められます。食品衛生法をはじめとする各種法令の遵守は、飲食店経営において絶対に避けて通れない責任です。
しかし、これらの管理や対応には多くの時間と労力、そして知識が必要となります。特に、2025年に完全施行されたHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の義務化により、その負担は以前より大きくなっています。

成功への戦略としては、まず衛生管理のシステム化と日常業務への組み込みが重要です。チェックリストの活用や、定期的な研修の実施により、スタッフ全員の衛生意識を高めることが基本となります。また、最新の法令情報を常に把握し、変更があれば迅速に対応できる体制を整えることも必要です。さらに、外部の専門家や保健所の指導を積極的に受け入れ、自店の衛生管理レベルを客観的に評価・改善していくことも効果的です。
法令遵守と衛生管理は店舗存続の必須条件です。基礎から最新の義務化内容まで、こちらで解説しています。
▶ 【2025年最新】飲食店が知っておくべき食中毒リスク5つ
理由10:精神的・肉体的負担の大きさ
飲食店経営は、精神的にも肉体的にも非常に負担の大きい仕事です。長時間労働や不規則な生活リズム、常にお客様と向き合うストレスなど、経営者自身の健康管理も大きな課題となります。
特に個人経営の飲食店では、オーナーが調理から接客、経営管理まですべてを担うケースも多く、その負担は計り知れません。この過酷な労働環境が、廃業の原因となることも少なくないのです。
ある経営者は毎日朝から深夜まで働き、休日も事務作業に追われる日々でした。ある日、突然体調を崩し、3週間ほど入院することに。この経験から、自分の健康管理こそが店舗運営の基盤であることを学びました。以降は、業務の効率化と権限委譲を進め、自分の時間を確保することを意識するようになりました。

成功への戦略としては、まず業務の効率化と標準化を進め、オーナー一人に依存しない店舗運営体制を構築することが重要です。信頼できるスタッフへの権限委譲や、外部サービスの活用なども検討すべきでしょう。また、定期的な休息と健康管理の時間を確保することを経営計画に組み込むことも必要です。さらに、同業者のコミュニティに参加し、悩みや課題を共有できる場を持つことも、精神的な負担軽減に効果的です。
あなたは自分自身の健康管理と、店舗運営のバランスをどのように取っていますか?
まとめ.飲食店経営を成功させるための5つの具体的戦略
ここまで飲食店経営が難しい10の理由をお伝えしてきましたが、これらの課題を乗り越え、成功に導くための具体的な戦略をご紹介します。
まず第一に、明確なコンセプト設計が不可欠です。「誰に、何を、どのように」を具体的に言語化し、競合との差別化ポイントを明確にしましょう。ターゲット顧客を絞り込むことで、効果的なマーケティング戦略を立てることができます。
第二に、徹底した数値管理を行いましょう。売上や原価、人件費などの数字を常に把握し、問題点を早期に発見・対応することが重要です。特にFL比率(食材費と人件費の合計÷売上)は、60〜65%を目安に管理することをおすすめします。
日々の売上や経費の管理を効率化することが、長期的な安定経営につながります。
第三に、人材育成システムの構築です。採用から教育、評価までの一貫したシステムを作り、スタッフの定着率と能力向上を図りましょう。特に、「なぜそれをするのか」という理由を伝えることで、主体的に考えて行動できるスタッフを育てることができます。
第四に、顧客との関係構築に注力しましょう。一度来店したお客様をリピーターに変えるための仕組みづくりが重要です。顧客情報の管理や、SNSを活用した継続的なコミュニケーション、会員制度の導入などが効果的です。
最後に、自己成長への投資を忘れないことです。業界の最新トレンドや経営ノウハウを学び続けることで、変化する環境に対応する力を養いましょう。セミナーや書籍、同業者との交流など、様々な方法で知識を更新し続けることが、長期的な成功につながります。
飲食店経営は確かに難しい挑戦ですが、これらの戦略を実践することで、多くの困難を乗り越えることができるはずです。
私は25年間、現場で様々な困難に直面してきましたが、その経験が今、皆さんのお役に立てることを嬉しく思います。一緒に、強くて愛されるお店を作っていきましょう!飲食店経営でお悩みの方は、ぜひ飲食業界で25年、「美味しい」と「楽しい」を追求し続けてきた飲食店経営伴走型パートナー岡本にevisu公式LINEにてご相談ください。
岡本優
飲食店経営伴走型パートナー
もう、一人で悩まない。
あなたの店の「右腕」になります。
利益改善、集客強化、人材育成、オペレーション改善まで、
経営のあらゆる課題に、オーナー様と同じ目線で
共に答えを見つけ出します。
現場力とマーケティング力を掛け合わせた、
evisuだけが提供できる継続的なパートナーシップです。
飲食店の課題の答えは、すべて現場にあります。
私の仕事は、その答えをオーナー様と共に見つけ出すこと。
飲食業界で25年、お客様の「美味しい」とスタッフの「楽しい」を追求し続けてまいりました。株式会社サッポロライオン「銀座ライオン」にアルバイトにて入社後、ひたすら経営と現場に没頭する中で、新宿店、そして800席を超える銀座本店の総支配人を拝命。
赤字店舗の再建を託される機会も多く、お客様とスタッフ双方の満足度向上を軸としたアプローチで、全ての担当店舗を黒字化へ導いた経験は、私の大きな財産です。
しかし、多くの飲食店が未来に不安を抱えている現状を目の当たりにし、この経験を業界全体のために活かしたいという想いが日に日に強くなりました。そこで2025年、株式会社evisuを設立。25年間現場で培ったリアルなノウハウを、同じ志を持つ経営者の皆様と分かち合い、共に困難を乗り越えるパートナーでありたいと考えております。
「楽しくなければ飲食店ではない」を信念に、皆様のお店が笑顔で溢れる場所になるよう、全力でサポートいたします。



