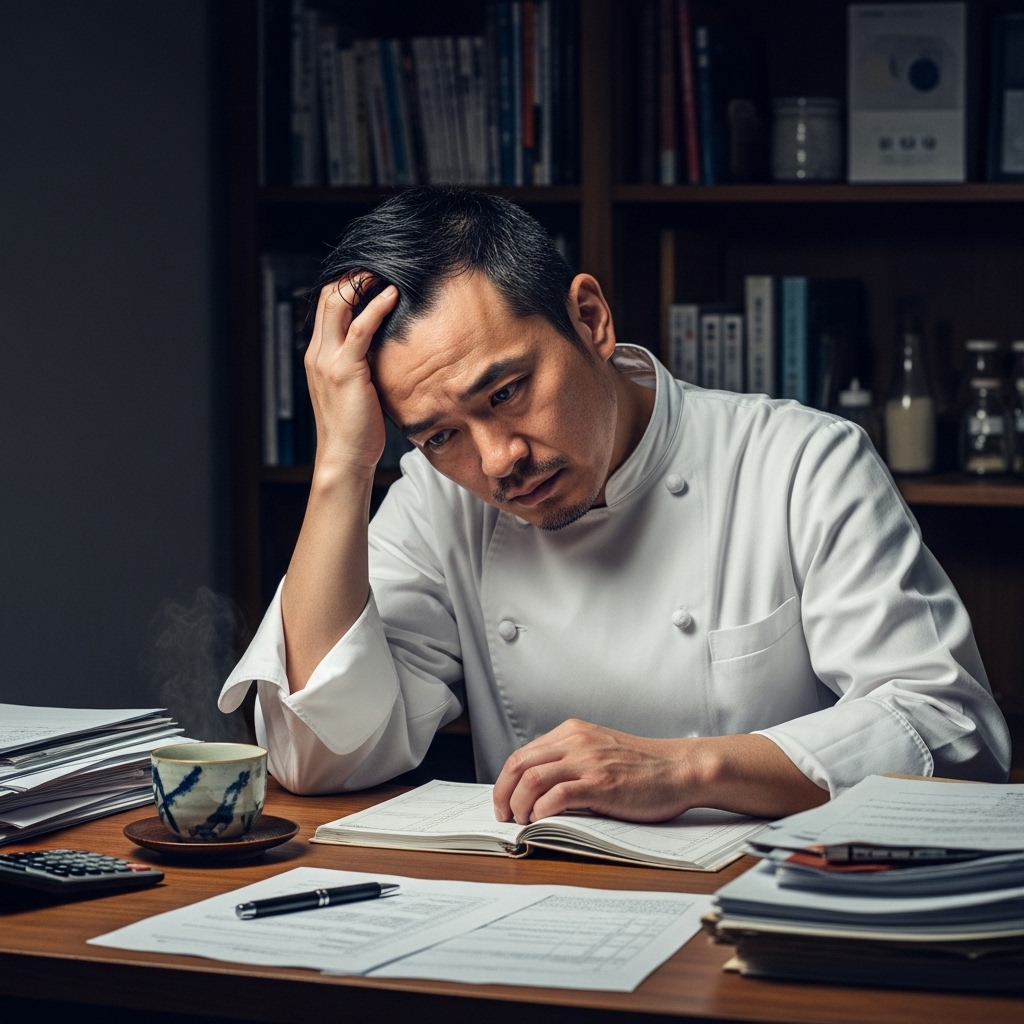こんにちは!飲食業界で25年、お客様の「美味しい」とスタッフの「楽しい」を追求し続けてきた飲食店経営伴走型パートナー、岡本です。今回は飲食店経営者にとって最も恐ろしい事態の一つ、「食中毒」について徹底解説します。
食中毒は発生してしまうと、お客様の健康被害はもちろん、店舗の信用問題や賠償責任まで発展する深刻な問題です。私も現場にいた頃、食中毒の発生を防ぐために神経をすり減らした経験があります。
お店で食中毒発生時に初期対応と緊急措置はどうすればいいのか?
まずは、万が一食中毒が発生してしまった場合の初期対応について見ていきましょう。初動の対応が適切かどうかで、その後の展開が大きく変わってきます。
食中毒が疑われる状況になったら、まず冷静に事実確認を行いましょう。お客様から「お店で食事をしてから体調が悪くなった」という連絡が入ったら、以下の情報を丁寧に聞き取ることが重要です。
| <お客様に伺うこと> ・来店された日時と人数注文された料理の内容いつからか ・どのような症状が出ているか ・一緒に食事をした方に同様の症状が出ているか ・お名前と連絡先 |
この時点では、まだ自店の料理が原因かどうか確定していません。しかし、疑いがある以上、決して否定せず、お客様の不安に寄り添う姿勢が大切です。「すぐに病院を受診してください」と促し、診断料は自店にて、もし自店が原因だった場合は、治療費など必要な費用を負担する旨を伝えましょう。
そして、すぐに所轄の保健所に連絡することを忘れないでください。保健所への報告は法的義務であり、自主的に連絡することで誠実な対応姿勢を示すことができます。もちろんお客様へもその旨伝えます。
保健所の立ち入り検査と行政処分の流れ
食中毒の疑いが生じると、保健所による立ち入り検査が行われます。これは恐れるものではなく、原因究明と再発防止のための重要なプロセスです。
私が大阪で店長をしていた時、近隣店舗で食中毒が発生し、保健所の検査の厳しさを間接的に見た経験があります。その時に学んだのは、日頃からの衛生管理の徹底と記録の重要性でした。
保健所の立ち入り検査では、主に以下のような調査が行われます。
立ち入り検査の際には、以下のような資料の提出を求められることが多いので、日頃から整理しておくことをおすすめします。
検査の結果、自店の料理が食中毒の原因と判断された場合、営業停止などの行政処分が下されることがあります。営業停止期間は原因となった病原体や被害の程度によって異なりますが、一般的には3日〜14日程度です。
とにもかくにも、保健所の調査には誠実に協力することが最も重要です。隠し事をしたり、虚偽の報告をしたりすると、さらに重い処分を受けることになります。
食中毒を未然に防ぐには、日頃からの衛生管理体制が欠かせません。食品衛生責任者の役割や具体的な管理方法についてはこちらで詳しく解説しています。
食中毒被害者へのお店側の賠償責任と対応すべきこと
食中毒が発生した場合、被害者に対する賠償責任が生じます。これは民法上の不法行為責任や債務不履行責任、さらには製造物責任法(PL法)に基づくものです。
一言でいうと、飲食店は「安全な食品を提供する義務」を負っており、その義務を果たせなかった場合は賠償責任を負うということです。
食中毒被害者に対して賠償すべき主な項目は以下の通りです。
特に重症の場合は、長期の入院や後遺症が残ることもあり、賠償金額が高額になることもあります。最悪の場合、死亡事故に至ることもあり、その場合は遺族への賠償も必要になります。
では、具体的にどのように対応すべきでしょうか?
まず、被害者からの連絡があった時点で、誠意を持って対応することが重要です。「うちの店のせいではない」という防衛的な態度は避け、まずは被害者の状況を心配する姿勢を示しましょう。
そして、保健所の調査結果が出るまでは原因の断定を避けつつも、被害者の治療費などの実費については、原因が確定する前でも一時的に負担を申し出ることも検討すべきです。
原因が確定した後は、誠実に賠償責任を果たすことが、店舗の信用回復につながります。ただし、賠償金額については、弁護士や保険会社と相談しながら適切な金額を設定することが重要です。
食中毒リスクに備える保険と法的対策
食中毒のリスクに備えるためには、適切な保険に加入しておくことが非常に重要です。実際、私が総支配人を務めていた大型店舗では、万が一の事態に備えて複数の保険に加入していました。
飲食店が加入すべき主な保険は以下の通りです。
特に生産物賠償責任保険(PL保険)は、食中毒が発生した場合の被害者への賠償金や弁護士費用などをカバーする重要な保険です。保険料は年間売上高や業種によって異なりますが、万が一の高額賠償に備えるためには必須と言えるでしょう。
また、近年では「タフビズ賠償総合保険」や「ALL STARs」といった、複数のリスクをまとめてカバーする総合的な保険商品も登場しています。これらは食中毒だけでなく、施設の欠陥による事故や従業員のミスによる事故なども幅広くカバーしているため、飲食店経営者にとって心強い味方になります。
参考元:タフビズ賠償総合保険(あいおいニッセイ同和損保)
参考元:事業賠償・費用総合保険(ALL STARs AIG保険)
保険に加入する際は、以下のポイントに注意しましょう。
保険は「入っておけば安心」というものではなく、いざという時に本当に役立つ内容になっているかを確認することが重要です。保険の専門家に相談しながら、自店に最適な保険を選びましょう。
また、万が一の食中毒発生時に備えて、弁護士との顧問契約も検討する価値があります。特に複数店舗を展開している場合は、法的リスクも高まるため、日頃から法律の専門家に相談できる体制を整えておくことをおすすめします。
食中毒以外にも、店内での嘔吐対応やクレーム処理など、突発的なリスク対応力が信用を守ります。具体的な対応方法についてはこちらをご覧ください。
▶飲食店での嘔吐対応マニュアル|感染拡大を防ぐ正しい処理方法は?
食中毒発生後の信用回復と再発防止策
食中毒が発生してしまった後、最も大きな課題となるのが「信用の回復」です。一度失った信頼を取り戻すのは、新たに信頼を築くよりもはるかに難しいものです。
私が福岡の店舗で働いていた時、近隣の有名店で食中毒が発生し、その後の信用回復に苦労している姿を見ました。その経験から、信用回復には「正直さ」と「具体的な改善策の提示」が何より重要だと学びました。
食中毒発生後の信用回復のために取るべき具体的なステップを紹介します。
特に重要なのは、原因の徹底究明と再発防止策の具体化です。「二度と同じ過ちを繰り返さない」という強い決意を、具体的な行動で示すことが信頼回復の第一歩となります。
例えば、以下のような再発防止策が考えられます。
また、営業再開時には、お客様に安心して来店いただけるよう、改善策を明示したポスターの掲示や、スタッフからの丁寧な説明なども効果的です。
信用回復には時間がかかりますが、誠実な対応と具体的な改善策の実行を続けることで、必ず信頼は戻ってきます。むしろ、危機を乗り越えたことで、以前よりも強固な信頼関係を築くことも可能です。
まとめ:食中毒発生時の対応と賠償責任の要点
食中毒は飲食店にとって最も避けたい事態の一つですが、万が一発生した場合に適切に対応できるよう、今回ご紹介した内容をしっかりと押さえておきましょう。
まず、食中毒が疑われる状況では、冷静な初期対応が何より重要です。お客様からの連絡に誠実に対応し、必要な情報を聞き取り、すぐに保健所への報告を行いましょう。
保健所の立ち入り検査には全面的に協力し、原因究明に努めることが大切です。そして、被害者に対しては誠意を持って対応し、適切な賠償責任を果たすことが信用回復の第一歩となります。
また、万が一の事態に備えて、適切な保険に加入しておくことも重要です。特に生産物賠償責任保険(PL保険)は、高額な賠償金から店舗を守る重要な防波堤となります。
そして何より大切なのは、食中毒発生後の信用回復と再発防止策です。原因を徹底的に究明し、具体的な改善策を実行することで、失った信頼を取り戻すことができます。
食中毒対策の原理原則は「予防」です。日頃からの衛生管理の徹底が最も重要ですが、それでも万が一発生した場合に適切に対応できるよう、この記事の内容を参考にしていただければ幸いです。
一緒に、安全で信頼される飲食店づくりを進めていきましょう!
食中毒対策や飲食店経営のお悩みがあれば、いつでもご相談ください。25年の現場経験を活かして、皆さんの店舗運営をサポートします。
飲食業界で25年、「美味しい」と「楽しい」を追求し続けてきた飲食店経営伴走型パートナー岡本にevisu公式LINEにてご相談ください。
岡本優
飲食店経営伴走型パートナー
もう、一人で悩まない。
あなたの店の「右腕」になります。
利益改善、集客強化、人材育成、オペレーション改善まで、
経営のあらゆる課題に、オーナー様と同じ目線で
共に答えを見つけ出します。
現場力とマーケティング力を掛け合わせた、
evisuだけが提供できる継続的なパートナーシップです。
飲食店の課題の答えは、すべて現場にあります。
私の仕事は、その答えをオーナー様と共に見つけ出すこと。
飲食業界で25年、お客様の「美味しい」とスタッフの「楽しい」を追求し続けてまいりました。株式会社サッポロライオン「銀座ライオン」にアルバイトにて入社後、ひたすら経営と現場に没頭する中で、新宿店、そして800席を超える銀座本店の総支配人を拝命。
赤字店舗の再建を託される機会も多く、お客様とスタッフ双方の満足度向上を軸としたアプローチで、全ての担当店舗を黒字化へ導いた経験は、私の大きな財産です。
しかし、多くの飲食店が未来に不安を抱えている現状を目の当たりにし、この経験を業界全体のために活かしたいという想いが日に日に強くなりました。そこで2025年、株式会社evisuを設立。25年間現場で培ったリアルなノウハウを、同じ志を持つ経営者の皆様と分かち合い、共に困難を乗り越えるパートナーでありたいと考えております。
「楽しくなければ飲食店ではない」を信念に、皆様のお店が笑顔で溢れる場所になるよう、全力でサポートいたします。